■加熱する「ふるさと納税」に対する考察
特典が話題となり、ガイドブックやノウハウ本が出版されるなど、「ふるさと納税」が過熱化しています。さらに2016年度の税制改正大綱に「企業版ふるさと納税」が盛り込まれ、関心度はますます高まりを見せています。税額控除や特典の利点に加え、「税金の使い道」を一人ひとりが考えるきっかけにもなっています。
 |
ふるさと納税とは
|
ふるさと納税とは、大都市圏に人口が集中し、地方の過疎化が問題となるなか、2008年の第一次安倍政権のもとで創設された制度です。「今は都会に住んでいても、自分の生まれ育った故郷の自治体に、いくらかでも納税できる制度があってもよい」という発想から生まれました。
納税と名付けられていますが、実際には都道府県、市町村への「寄付」であり、支払い時に寄付金の使い道を選んで指定できるのが特徴です。「ふるさと」と名付けられていますが、納税先の自治体は生まれ故郷でなくてもかまいません。
 |
ふるさと納税が人気となった要因・背景
|
一般的な寄付であっても、確定申告をすれば、その寄付の一部が所得税や住民税から控除されます。ふるさと納税では寄付した金額に対してその控除額が大きく、さらに各自治体から特産物(記念品)がもらえるお得な制度です。
例えば1万円のふるさと納税をすると、自治体から4,000〜5,000円相当の特産品がもらえます。所得税の還付や住民税の控除額を合計すると8,000円になり、実質は2,000円の支払いで4,000〜5,000円のものを手に入れることができるのです。
一方で、各自治体ではこの寄付金集めや地元の特産品をアピールするため、その収支が見合わないような豪華な特産品を用意するところが相次いでおり、さらにこれをメディアがあおり、過熱しすぎているという意見がでてきています。
 |
企業版のふるさと納税について
|
昨年発表された2016年の税制大綱に、企業に対して地方自治体への寄付を促し、地方活性化につなげる「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制、2016年度から19年度までの時限措置)」が織り込まれました。大綱では、「地域再生法の改正を前提に、地方公共団体の行う同法の認定計画に記載された一定の事業に関連する寄附金を支出した場合の税額控除を創設」と記載されています。
国税庁からの統計資料によると、法人が支出した2013年の「国や地方公共団体に対する寄付金」は1,874億円あり、法人所得の0.3%の割合を占めていました。一般的な寄付金と異なり、「国や地方公共団体に対する寄付金」の扱いは、これまでも全額が損金に算入することができたため、実質負担は約7割ほどでした。
企業版ふるさと納税は、政府が認定した自治体の活性化事業に寄付をすれば、寄付額の3割が法人業税、住民税、法人税、の法人3税から税額控除されるという仕組みで、現行の「寄付税制」による全額損金算入の約3割と合わせて、約6割の税金が軽減されることになります。
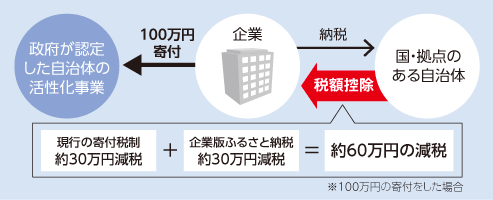
今回の企業版ふるさと納税が制定された場合、この全額損金算入に加え、国税・地方税の税額控除を導入し、法人が支払う税金は、実質負担は約4割へ軽減されることになります。
この税金負担の軽減が実現すれば、寄付金はさらに増えると予想されます。ただし、金額も個人とは比較にならないため記念品はさらに豪華さを増す可能性や、企業と自治体の癒着・政治利用として使われる恐れなどもあり、規定や本来の寄付の趣旨を通せるかが政府の運用のポイントになると考えられます。
 |
今後の動向 |
ふるさと納税は、地方の活性化、税額控除、特典等のメリットが注目されがちですが、「税金の使い道を自分で決める」という視点もあります。これまでは、社会的・公共的なサービスは行政によるものが主流で、その多くは税金で賄われてきました。しかし近年の日本では、財政赤字、少子高齢化、貧困の拡大などの面で「課題先進国」となりつつあります。経済の縮小と、それに伴う税収の減少によって、「行政がなんでもしてくれる」ことが当たり前ではなくなる可能性も否定できません。
企業版ふるさと納税によって、ふるさと納税はさらに関心を集めそうです。現在、ふるさと納税は過熱しすぎているとも言われますが、そもそもの趣旨通り、国民一人ひとりが社会課題に向き合って、それをどう解決すべきかを考え、その税金の使い道を自ら指定していくきっかけにもなっています。