海外進出がビジネスの通例に
土俵は中国・ASEANへ
経済成長の指標となる日本のGDP(国内総生産)は、2013年度で483.1兆円(名目国内総生産)となり、前年度の474.5兆円と比べ、成長率は1.8%とプラスを更新したものの、ここ数年の数値はほぼ横ばいの推移であり、日本経済の成長が鈍化していることが見て取れます。さらに、人口減による支出額や労働人口の減少、飽和状態にある市場の縮小、金融危機の景気悪化など、企業を取り巻く環境は決して安泰とは言えず、将来への不安は拭いきれません。しかし手をこまねいていては成長ばかりか企業の存続すら揺らいでしまいます。
そうした状況下、ビジネスは海外、特に人口の増加、購買意欲やGDPが高まる中国・ASEANへの進出が目立っており、多くの日本企業が魅力的な市場と捉えています。事実、海外進出が一巡したと言われる昨今でもその数は年々増え、2012年度の海外現地法人数は23,351社と、ついに2万社の大台を超えました(図1)。国別では中国が3割強とダントツで、65%以上がアジアに集中しています(図2)。景気減退とささやかれる中国ですが、今なお市場が大きいことがうかがえます。
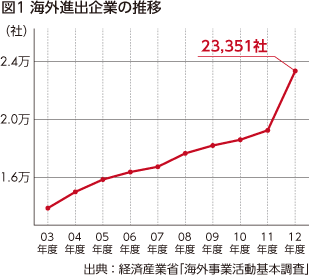
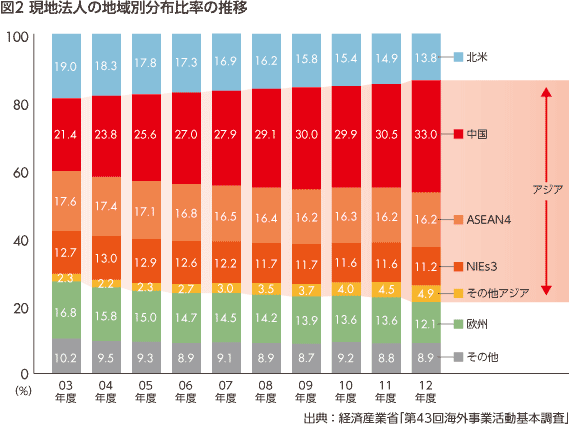
現地法人との経理業務のやり取りの
改善で海外展開の成功を維持する
魅力的に映る海外進出も、もちろん撤退や撤退検討を余儀なくされるケースはあります。ある民間調査会社によるアンケートでは、撤退・撤退検討時の課題に対し、順に「資金回収」「(現地従業員の)処遇」「法制度・会計制度・行政手続き」という回答がありました。グローバル化と言われても、現地の慣例や複雑な制度に対応することは決して容易ではないのです。本特集では、課題の中でも挙げられた「会計制度」、つまり現地の経理業務について着目し、進出規模の大多数を占める中国を例に有識者のコメントを元に解決の糸口を探っていきます。
日本政府は成長戦略の1つに2020年までに輸出額を2010年の2倍にする目標を掲げ、中堅・中小企業の海外進出を積極的に支援しています。企業規模を問わず「海外進出は関係ない」と言えなくなってきた今、現地法人の財務会計情報を無駄なく正確にタイムリーに把握し、経営戦略に活用するレポーティングを作成することが海外進出の成功を手中に収める重要なファクターとなっています。では、現地法人との経理業務のやり取りの問題を解決するにはどのような策を講じればよいのでしょうか。
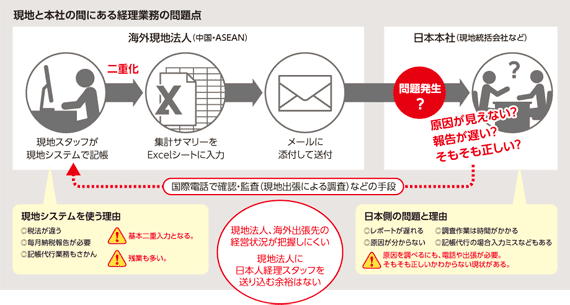

情報網の発展により、世界のあらゆる情報を日本にいながら手に入れることができるようになりましたが、世界の門扉がいくら開いても、他国を理解することは容易ではなく、知れば知るほどその難しさを痛感します。まして海外に進出して会社を現地に根づかせるには、体力、知識、資金、経験などたくさんの要素を必要とします。日本経済の成長が鈍くなる中、海外進出をためらっている時間はありません。そこで今回、中国・アジアに進出する日系企業約3,500社の支援実績を持つマイツグループCEO・公認会計士の池田博義氏に、経験から学んだ海外ビジネスを成功に導くヒントについて経理業務を中心にお聞きしました。


1948年京都府生まれ。71年同志社大学経済学部卒業。75年公認会計士資格取得と同時に池田公認会計士事務所、税理士池田博義事務所開設。87年には株式会社マイツを設立、代表取締役に就任する。94年株式会社マイツ上海駐在員事務所開設、首席代表に就任。99年には上海マイツ咨詢有限公司を設立、董事長に就任。現在は中国沿海部に
マイツグループ
の事業所を展開し、日本国内の会計・税務・財務支援のみならず、中国・アジアに進出する日系企業の経理業務支援をはじめ、様々なコンサルティング業務を行っている。同グループが支援する中国・アジア進出の日系企業数は3,500社以上にのぼり、中国における幅広いビジネスの実績と経験を持つ。
すべての企業が海外と関わる可能性がある
1993年、私は単身上海に乗り込み、この地で中国に進出する日系企業の応援をしようと決意しました。あれから22年、多くの成功、そして失敗を見てきました。日系企業における中国進出の歴史は、80年代までの国家プロジェクトに代表する重工業関連に始まり、90年代のアパレルを中心とする軽工業、2000年代では通信や飲食、最近では環境や介護、メンタルヘルスとビジネスの中心が変わってきました。大型産業から小型生産へ、そしてサービスへとシフトし、大企業から中堅・中小企業まで企業規模に関係なくビジネスの場を中国に置く企業が増えています。縮小する国内市場や海外進出企業の増加を背景に、どんなに小さな企業であっても、直接的・間接的に海外と関わらざるを得ない状況が発生しています。でも海外との関わりで苦労する部分も多く存在します。そのひとつが経理業務です。
|
“月次報告なんて関係ない”中国の習慣
中国にはきちんと納税する意識があまりありません。というのも、かつて外商投資企業は法人税が15%と、中国国内企業の33%に対して大きな優遇を受けており、内資企業は経費を水増ししたり売上を削って見積もったりしなければ競争ができなかったのです。また、93年当時の中国は現金商売であり、入金があった時に売上を計上し商品代金を支払い、払った時に仕入を立てるやり方でした。日本のように発生主義の信用取引ではなかったのです。現在は国際会計基準が導入されて2008年には外資内資に関わらず法人税は25%と定められ、税制が整備されたので制度的な問題は解決しつつあります。しかし、中国のバックオフィスにはもっと大きな問題がありました。それは、月次報告がキチッとしていないことです。納税は四半期に一度行われているものの、年度監査しかなく、試算表を作るにしても伝票をとりあえず集めて明細を作るので、後でチェックをすると間違っていることが多々あります。正確性が怪しい情報は何の意味もありません。それが、日系企業が頭を抱える問題となっています。
|
勘定奉行で現地の数字を確認できる仕組みを
中国では「金蝶(きんちょう)」と「用友(よんよう)」のどちらかの会計ソフトが使われるケースが多いのですが、勘定奉行との直接的な互換性はないため、会計情報サマリーを提出する際は、Excel等に二重入力をするやり方が主流です。もちろん、コンバータツールを導入する、グローバル対応のソフトを使う、外部委託をするなど、方法はいくつかありますが、月々のコストが高かったり、操作レベルが高く使いこなせなかったり、高いハードルがあります。とは言え今の時代、リアルタイムで正しい情報を把握できないことを「日本とは違うから」の一言で済ませられないでしょう。正確な情報をもとに事業の見通しを立て、ビジネス戦略を練るというのは当たり前です。また、現地の日系企業を見ていると、本社から営業担当の駐在員に「売掛金・買掛金はどうなっているのか」「現地の試算表は合っているか確認を」と本来の業務に専念できない状況を作っている場面に遭遇します。経理担当者を気軽に派遣できないことはよくわかりますが、これでは本末転倒ですね。このような場面を少しでも減らし、使い慣れた勘定奉行で現地の正確な財務会計状況をリアルタイムで確認できるOBCの「 奉行海外法人コネクトサービス
」は問題解決の有能なツールであり、価値あるサービスだと思います。資金コントロールにも役立つでしょう。
|
現地化を進め情報のチェック体制を強化
これからの海外ビジネスを軌道に乗せる2つのキーワードがあります。それが「現地化」と「管理体制」です。「現地化」とは、経営を現地に任せる度量を持つこと、ミッションを与えても独立性を持たせることです。現地を知らずに日本で作戦を立ててもうまくいかないことが多いからです。進む「現地化」を支えるのは信頼性です。そこで「管理体制」が重要になります。不正はないか、間違いはないかをチェックできる体制がしっかりしていれば安心して現地に任せられます。それにはやはり経営の要である経理業務のチェックができる仕組みを構築することです。先に挙げた「 奉行 海外法人コネクトサービス
」は、海外進出に必要な「現地化」と「管理体制」を実現する仕組み作りの構築への貢献度は高いと言えます。
|