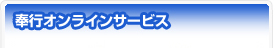�����x�y�ыƖ��̑z��X�P�W���[��
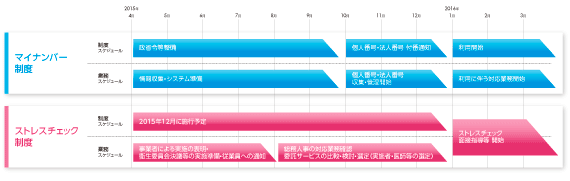
�@�}�C�i���o�[���x�Ƃ́A�}�C�i���o�[�i�Z���[�������ׂĂ̐l�ɕt�Ԃ����l�ŗL�̔ԍ��j�𗘗p���ĐłƎЉ�ۏ��R�Â����A�葱���̊ȑf���E�v������}��A�������Ō����ȎЉ��ڎw�����x�ł��B���Ԋ�Ƃɂ͖@�l�ԍ����t�Ԃ���܂��B
| �Ώۊ�� |
���ׂĂ̊�� ���@�l�ԍ��͖��Ԋ�Ƃ̂ݕt�Ԃ���܂��B |
| ��ȑΉ��Ɩ����� |
�l�����E������ |
| ���� |
2015�N10���` �ʒm�E�t�ԊJ�n
2016�N1���` ���p�J�n |
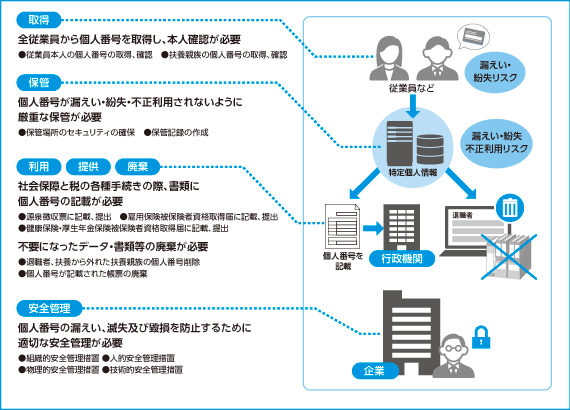
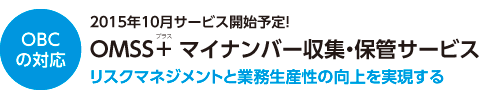
�@OBC�ł́A�l�ԍ��̎擾�A�ۊǂ̍ۂɋN���肤�郊�X�N��ጸ���邽�߂ɁA�V���ɃT�[�r�X�Ƃ��āu�}�C�i���o�[���W�E�ۊǃT�[�r�X�v����܂��BOBC�̃}�C�i���o�[�Ή��V�X�e���͖@�ߑΉ������łȂ��A�l�ԍ��̎擾�E�ۊǂ��痘�p�E�E�p���܂ŁA��Ƃ̃��X�N�}�l�W�����g�ƋƖ����Y���܂ōl�������Ή����Ɏ����ł��܂��B�A�������s�V���[�Y�Ƃ��킹�Ă����p�����������Ƃ�����Ă������܂��B
�@���Ǝ҂ɑ��āA�X�g���X�`�F�b�N���x�i�J���҂̐S���I�ȕ��S�̒��x��c�����邽�߂́A��t�A�ی��t���ɂ�錟���̎��{�j���`��������܂��B�����^���w���X�̈ꎟ�\�h����ȖړI�Ƃ��鐧�x�ł���Ɠ����ɁA�J���҂̃Z���t�P�A�A�E������P�̑��i�Ƃ����������ɂȂ��Ă��܂��B
| �Ώۊ�� |
50�l�ȏ�̎��Ə��L������
���]�ƈ�50�l�����̎��Ə�ɂ��Ă͓����̊ԓw�͋`���Ƃ���B |
| ��ȑΉ��Ɩ����� |
�l�����E������ |
| ���� |
2015�N12���Ɏ{�s
���X�g���X�`�F�b�N�̎��{�͌����N1�� |
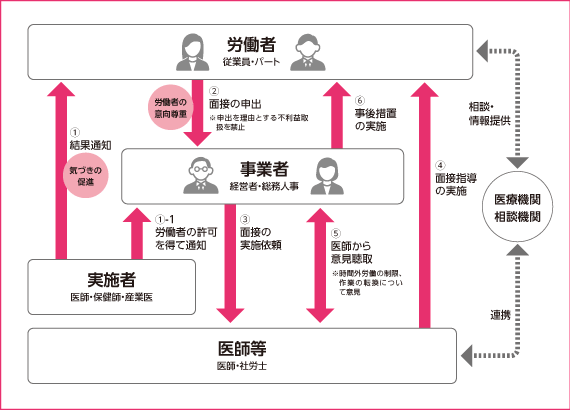
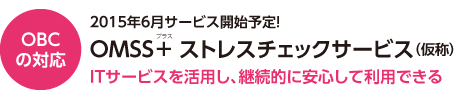
�@�����E������Ƃ���y�ɁE�p���I�ɁE���S���ė��p�ł���X�g���X�`�F�b�N�T�[�r�X�ł��B�X�g���X�`�F�b�N�@�����ɏ������AIT�T�[�r�X�Ɖ^�p�m�E�n�E�����킹���X�^���_�[�h�ȉ^�p���@�𒆏��E������ƌ����ɒ��܂��B���\�z�̎�Ԃ��v��Ȃ��N���E�h�x�[�X�ŁA�Ј����ɉ������������₷�����i�тŃ����[�X��\�肵�Ă��܂��B
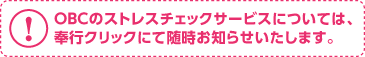
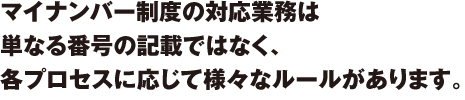
�@2016�N1���A�Љ�ۏ�E�ł̕���Ōl�ԍ��i�}�C�i���o�[�j�Ɩ@�l�ԍ��̗��p���J�n����܂��B���́u�}�C�i���o�[���x�v���n�܂�ƁA�l���E��������őΉ��Ɩ����V���ɕK�v�ƂȂ�A�l�X�ȕ��S�������邱�Ƃ��\�z����܂��B
�@�}�C�i���o�[�̕t�ԁE�ʒm�܂Ŕ��N����Ă��܂����A�����̊�Ƃ́u�܂��������W���Ă���i�K�v�Ƃ����ł��B�Ƃ͌����Ă��A���낻���̓I�ȏ������n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɓ����Ă��Ă���̂�����ł��B�}�C�i���o�[���x�̋Ɩ��v���Z�X�����Ȃ���Ή��Ɩ��ƁA����ɔ������ӓ_���m�F���Ă����܂��傤�B
�@�擾
�}�C�i���o�[�̑Ή��Ɩ��́A�擾����n�܂�܂��B���Ј������łȂ��A���Ј��A�p�[�g�E�A���o�C�g�Ƃ������Ј�������}�C�i���o�[�����W���܂��B�܂��A�}�{�Ƒ����V���x�����L���ҁE�O���X�^�b�t����̎擾���K�v�ƂȂ�܂��B
�����O�����c�}�C�i���o�[���W�܂�Ȃ��A�}�C�i���o�[�̎擾�E�m�F�R��A�����Ǘ����̎�ԁA�l�ԍ��R�������X�N �Ȃ�
�A�ۊ�
�}�C�i���o�[���擾������͕ۊǍ�Ƃ��������܂��B�ۊǂɍۂ��ẮA�}�C�i���o�[�̘R������s�����p�ɑ��郊�X�N�Ǘ��A�^�p�Ď��̑̐�����������K�v������܂��B
�����O�����c�ۊǂɔ����ԍ��̘R�������X�N�A�@�߂ɑ������ۊǂ��K�v �Ȃ�
�B���p�E�E�j��
���ۂɃ}�C�i���o�[�������Ɏg�p����ꍇ�́A�@�ߏ���͐�ł��B�}�C�i���o�[�͓���l���ɂ�����A��߂�ꂽ���p�͈̔͂��Ďg�p���Ă͂Ȃ�Ȃ����܂肪����A���Ȃ������ꍇ�͔���������܂��B�s�v�ɂȂ����}�C�i���o�[���R��Ȃ��j�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�����O�����c���p�͈͂̐����A�K�v�ȏ��ނւ̋L�ژR��A�p���R�� �Ȃ�
�C���S�Ǘ�
�}�C�i���o�[�̘R�����A�����A�ʑ��̖h�~�ȂǁA�K�ȊǗ��̂��߂Ɉ��S�Ǘ��[�u���u����K�v������܂��B
�@���̂悤�Ƀ}�C�i���o�[���x�̑Ή��Ɩ��́A�u�ԍ���K�v���ނɋL�����邾���v�ł͂Ȃ��A�u�}�C�i���o�[������l���ł��邱�Ƃ�F�����Ă�������Ɩ@�߂���邱�Ɓv�A�u�Ɩ��v���Z�X���ӎ����ă~�X�△�ʂ��������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ɓv����ɂȂ��Ă��܂��BOBC�ł́A�}�C�i���o�[���x�ɔ������X�N��ጸ���A�Ɩ������S�����m�E�����I�ɍs����悤�ɁA��s�V���[�Y�ƃT�[�r�X��������܂��B
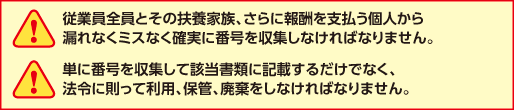
�@�}�C�i���o�[�̑Ή��Ɩ��ɂ��āu�]�ƈ�����ԍ��������Ă�����āA�Y�����鏑�ނɋL�����邾������Ȃ��́H�v�ƍl���Ă��܂��B�������A�K�v�Ȕԍ������W���ďƍ�����ɂ͖c��ȘJ�͂Ǝ��Ԃ�������A����Ƀ}�C�i���o�[����舵���ɂ́A�l�X�Ȍ��܂育�Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B�Ή��Ɩ��́A���L��3���N���A���邱�Ƃ����߂��܂��B

�@OBC�́A�l�ԍ��̎擾�A�ۊǂ̍ۂɋN���肤�郊�X�N��ጸ���邽�߂ɁA�V���ȃT�[�r�X�Ƃ��āuOMSS+�}�C�i���o�[���W�E�ۊǃT�[�r�X�v����܂��BOBC�̃}�C�i���o�[�Ή��V�X�e���͖@�ߑΉ������łȂ��A�l�ԍ��̎擾�E�ۊǂ��痘�p�E�E�p���܂ŁA��Ƃ̃��X�N�}�l�W�����g�ƋƖ����Y���܂ōl�������Ή����Ɏ����ł��܂��B
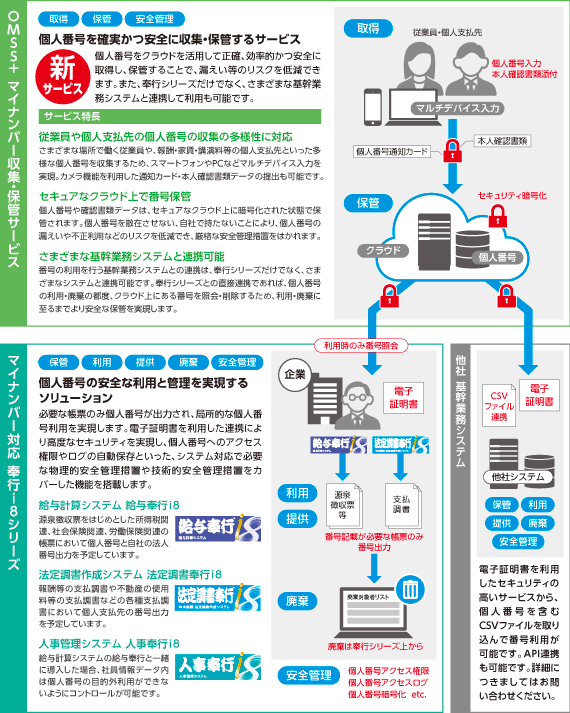
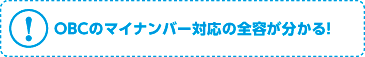
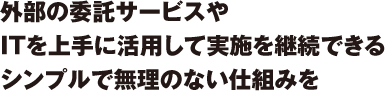
�@2015�N12���Ɏ{�s���\�肳��Ă���X�g���X�`�F�b�N���x�̎��{�J�n��O�ɁA�m���Ă����������x�̗���ƃ|�C���g�ɂ��āA��Ƃ̃����^���w���X���E����P�̎x���Ɍg�����v���c�@�l�J���Ȋw���������ʌ������i�E��h�b�N�x���`�[���j�̋g��x�q���ɂ��������܂����B�X�g���X�`�F�b�N���x�̖ړI����𗝉�����Ɠ����ɁA���{�̎d�g�ݍ��̃q���g��T��܂��B
���X�g���X�`�F�b�N���x�̗���}

�d�g�݂̃|�C���g
�@�@�ߏ���͐�@�A�J���҂̌��������@�B���G�łȂ��V���v���Ȏd�g��
�C���Ǘ�����������s���@�D���{�ҁE��t�������ɂ߂�@�E�M���W���d�v
|
������̎��g�݂̗���
�@���Ǝ҂����{�̕\����������A�q���ψ���ɂč���̎��g�݂ɂ��Č�������J���A�����Ō��܂������j�̂��ƁA���{�Ɍ������������s���܂��B���N��12���Ɏ��{����ꍇ��8���܂łɎ��{�������n�߂����Ƃ���ł��B�]�ƈ��ɑ��Ắu���܂������ƂȂ̂Ŏ�f�����肢���܂��v�Ǝ������̂ł͂Ȃ��A��|��ړI���������藝�������A��ۂƂȂ��Ď��g�݂܂��傤�B�ɖZ���ɃX�g���X�`�F�b�N�����{����ƁA�X�g���X�������Ɗ�����Ј��������Ȃ�\��������܂��̂ŁA�ł���ΔɖZ���͔�����̂��ǂ��ł��傤�B���{�͔N1��Ƃ���Ă��܂����A�J�g�����ӂ������ȏ�̉����{�\�ł��B

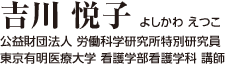
2002�N���C��w��w�@���N�Ȋw�����ȊŌ�w��U�C���B���N�ANTT�����{��s�����N�Ǘ��Z���^�ی��t�A06�N�����v���c�@�l�J���Ȋw�������������Ƃ��ċΖ��B�l���s�Ō��Ñ�w�Ō�w�������i07�N�j���o�āA11�N����͓����L����Ñ�w�Ō�w���̍u�t�߂�B�����Ɂw�����ɖ𗧂Y�ƊŌ�A�Z�X�����g�c�[���x�i�����j�A�w�Y�ƁE���_�Ō�̂��߂̓����l�̃����^���w���X�s���̗\�h�Ƒ����x���x�i�����j�Ȃǂ�����B
�E��h�b�N�x���`�[��
���v���c�@�l�J���Ȋw�������ɐݒu���ꂽ�����^���w���X�ꎟ�\�h�̂��߂̎Q���^�E������P���x������v���W�F�N�g�`�[���B��t�E�ی��t�E�l�ԍH�w���ƁE�Տ��S���m�E��Ɗ�����m�Ȃǂ̊w�ۓI�ȃ����o�[����\������A���Ə�ł̐E��h�b�N���{�Ɋւ���Z�p�I�T�|�[�g�A�����^���w���X�ꎟ�\�h�ɂ�����E������P�Ɋւ��R���e���c�̒Ȃ�тɌ��C�E�[�����Ƃ��s���Ă���B
�����^���w���X��̎��g�ݏ�
�@2013�N�Ɏ��{���ꂽ�����J���Ȃ̒����ɂ��ƁA�����^���w���X������{���Ă����Ƃ͖�6���ɂƂǂ܂��Ă��܂��B�����^���w���X��̏d�v����K�v�������܂��Ă������ŁA��4���̊�Ƃ��A�u�K�v���������Ȃ�����v�u�Y������]�ƈ������Ȃ�����v�Ȃǂ̗��R�Ń����^���w���X��Ɏ��g��ł��Ȃ��Ɖ��Ă��܂��B���̂��Ƃ���A�ꕔ�̊�Ƃł̓����^���w���X����u�a�C�̔����⎡�ÂɂȂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���v�Ƒ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
|
�X�g���X�`�F�b�N�@�����̖ړI
�@����`���������X�g���X�`�F�b�N���x�́A�a�C�̑���������a�C�̐l���܂ݏo���ړI�Ŏ��{�����̂ł͂Ȃ��A�u�����^���w���X�̈ꎟ�\�h�v�A�܂�J���҂̃Z���t�P�A��E������P�𑣂����x�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���_��Y��Ă͂����܂���B�E��ɂ���S���ɏ��⋳�猤�C���s���A�E��̃����^���w���X�̎��g�݂�����O�ɐi�߂��D�̋@��ł���ƍl����Ɨǂ��ł��傤�B������f���̂̌��f�ł���̂ɑ��A�X�g���X�`�F�b�N���x�́u�S�̌��N�f�f�v�Ƒ�����Ƃ킩��₷����������܂���B
|
�X�g���X�`�F�b�N���{�O�̏���
�@��Ƃ��X�g���X�`�F�b�N�����{���邤���Œ��ӂ��ׂ����Ƃ�����܂��B����́A�u�X�g���X�`�F�b�N�̌��ʂ�{�l�̓��ӂȂ��ɊJ���E�{�����Ă͂����Ȃ����ƁA���̌��ʂ��{�l�̕]����ٗp�ɉe�����Ă͂����Ȃ����Ɓv�ł��B�X�g���X�`�F�b�N���x�͔��ɋ@���ȏ�����舵�����߁A�����ɘJ���҂̌�������邩�Ƃ����c�_�̂��ƁA��������܂łɎ���4�N�ȏ�̍Ό���������ꂽ���x�ł��B���̂��߂Ɏ��{�J�n�O�ɂ͕K���u���Ǝ҂ɂ����{�̕\���v���s���A�@���{�ړI�A�A���{���e�A�B���{�ɍۂ��Ă̖i��������ی쓙�j�A�C�t�H���[�̐��Ȃǂm�ɂ��܂��B
|
�X�g���X�`�F�b�N�^�p���̃|�C���g
�@���x�̗���ƁA�J���ҁA���ƎҁA���{�ҁA��t����4�҂̊ւ�肪���G�ŁA���{�̒蒅�܂łɂ͎��s���낪���邩������܂���B�A�ƋK���̕ύX���K�v�ȏꍇ�́A�ИJ�m�̋��͂��K�{�ł��B���{�ҁE��t����I�ԍۂ́A�u��Ƃ̂��Ƃ���ɍl���Ă���邩�ǂ����E�E������ǂ����邽�߂̃T�|�[�g�����Ă���邩�ǂ����v�����ɂ߂܂��傤�B
|
�����E������Ƃɋ��߂���̐�
�@�X�g���X�`�F�b�N���x�͖@�ߏ��炪��ƂȂ�܂����A�@�߂͕��G�ŗ������ɂ����ꍇ������A�ύX������������s���܂��B�X�g���X�`�F�b�N��1��ŏI���̂ł͂Ȃ��A���̌�̗\�h����܂߂č��ジ���Ƒ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA�V���v���ł킩��₷���A���{�ɖ��������Ȃ����Ƃ��p���̃|�C���g�ł��B������l���̊m�ۂɗ]�T�������Ƃł���A���͂ŃX�g���X�`�F�b�N���x�̎d�g�݂��\�z�ł��邩������܂��A������Ƃł͎���������ꂽ���ʼn^�c������Ȃ���������܂���B
|
�p�b�P�[�W�����ꂽ�T�[�r�X�̊��p
�@�����Ŋ��p�������̂��A�u�p�b�P�[�W�����ꂽ�O���̈ϑ��T�[�r�X�v�ł��B�O����EAP�i�]�ƈ��x���v���O�����j�ȂǁA������x���Ƃɂ��C�����邱�Ƃ��������ėǂ��Ǝv���܂��B�p�\�R����g�ѓd�b�A�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�[���Ȃǂ�ICT�i���ʐM�Z�p�j�ŃX�g���X�`�F�b�N�����{�ł���̐����x������T�[�r�X����������A�C�y�Ɏ邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ł͎�f���A�b�v�ɂȂ��邩������܂���B����͘J���҂�50�l�����̎��Ə�͓w�͋`���ƂȂ�܂������A�S�Ă̎��Ə�ւ̋`���������z�������������łɎn�܂��Ă��܂��B�J���҂����C�ȐS�g�ł��������Ɠ�����E�����Ǝ��g�����グ�Ă������Ƃ���ł��B
|