|
知っておきたい
最新の人事労務業務のトレンドキーワード
人事労務管理はトレンドの移り変わりが頻繁で、対応項目も多いため、見逃してしまう可能性があります。しっかりとトレンドキーワードを押さえ、抜け・漏れを予防するためにも、早めの対応準備が求められます。直近のトレンドキーワードにはどのようなものがあるのでしょうか。早速、確認していきましょう。
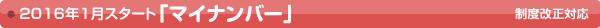
マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する個人と、法人に対して特定番号が割り当てられ、様々な行政手続きで利用される制度です。個人番号は2015年10月から通知が開始され、2016年1月からは社会保障、税、災害対策の分野で利用がスタートする予定です。
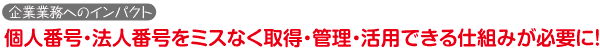
個人番号 : 正社員だけでなく、パートやアルバイト、従業員の家族(被扶養者)も対象です。本人確認資料の提出と管理が必要です。
法人番号 : 法人単位の法人番号があります。取引先等の法人番号管理と事務手続資料へ法人番号を記載します。

メンタル不全による労災認定や損害賠償訴訟が増加するなか、メンタルヘルス対策の充実・強化を目的として、法的義務化が2014年6月25日に公布されました。これにより、従業員50名以上の事業場には「定期的なストレスチェック」が2015年12月より義務づけられます。

◎年1回は社員にストレスチェックの実施と判定結果を通知。希望者には医師の面接指導を実施します。
◎企業側は、受診や面接結果の履歴を管理し、分析・対策・予防を講じます。
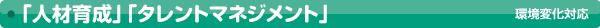
少子高齢化、65歳雇用義務、働き方の多様化などの職場環境の変化に伴い、有能な人材を確保する 「人材育成」は企業の生命線です。個々の社員に対して目指すべき人材と育成プランを提供する「タレントマネジメント」の導入が進んでいます。

◎社員の資質を「人材情報」として集約し、組織的に分析する必要があります。
◎個々の社員が目指すべき人材と育成プランを具体的に作成します。
◎育成結果を人事情報として管理し、人事考課や人事異動に反映します。
絶賛開催中の「奉行フォーラム2014」にて、総務業務トレンドに関わる展示・セミナーを実施しています。イベントに関する情報は
特設サイト
をご確認ください。
準備必須の社会保障・税番号制度
マイナンバー
2015年10月に開始される「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」の付番・通知まで1年を切りました。マイナンバーについては、ようやくその名が知られるようになったところで、企業における対応準備は、まだ十分とは言えない状況です。しかし、実施に際しては、源泉徴収票の作成、厚生年金保険、雇用保険、健康保険など、業務に関わる多くの場面で番号の利用が予定されており、企業のマイナンバーへの対応は必須です。今回は、マイナンバーについての概要や仕組み、利用例等を解説するとともに、マイナンバー利用までの大まかなスケジュールを確認していきます。
マイナンバーとは?
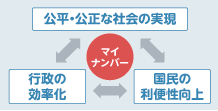
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持つすべての人に付番される個人固有の番号です。住所地の市町村長が指定し、一度指定された番号は原則として生涯変わることはありません。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)については、2010年2月に検討会が設置され、13年5月に成立しました。マイナンバー制度の成立には、社会保障の充実が急務となってきた社会背景があり、その実現には、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報を連携させる必要性があったためとされています。個人情報とマイナンバーを紐づけすることで、効率的・迅速的に情報管理を行い、複数の機関との間での確実な情報連携が期待できます。また、法人等には「法人番号」が付番されます。
マイナンバーの導入メリットは?
マイナンバーの導入メリットは、一言でいえば、「社会保障と税に関する申請や提出の手続きに伴う負担・不備の軽減による公平で公正な社会基盤の構築」です。これまでは、年金、雇用保険、医療保険等の社会保障分野と、確定申告、届出書、調書等の税分野との間には、連携性に不十分な部分や行政手続きの負担がありましたが、マイナンバーの記載により、複数の機関が連携し、利用者の負担が軽減され、公平な社会保障が受けられると期待されています。勤務先や保険会社などが利用者に代わって手続きを行う場合は、代行者にマイナンバーを提出します。
マイナンバーを利用することで、所得証明書や住民票の添付省略ができたり、異なる制度間の給付調整が確実に行えたりと、様々なメリットがあります。また、マイナンバーのカードを取得すれば、図書館利用や印鑑登録証などの自治体が条例で定めるサービスのほか、身分証明書としての利用も可能になります(ただし、マイナンバーの書き写しやコピーには制限があります)。
企業のマイナンバー対応と業務
 (1)従業員のマイナンバー取扱いについて (1)従業員のマイナンバー取扱いについて
企業では、事業規模に関わらず、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得して、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載し、行政機関などに提出する作業が発生します。また、支払調書等にも記載が必要になるので、事前にどの書類や手続きにマイナンバーの記載が必要なのかをしっかり把握しておきましょう(記載する必要のある帳票については、関係省令によって詳細が規定され、今後順次公布される予定です)。ただし、身分証明書としての本人確認、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外でマイナンバーを利用することはできないため、書き写しやコピー、保管には注意しましょう。
(2)法人番号について
社会保障・税番号制度には、住民票を有する個人番号であるマイナンバーと、国の機関、地方公共団体、設立登記法人、規定する届出書を提出することとされている法人または人格のない社団等に付番される法人番号があります。法人番号は、数字のみで構成される13桁の番号で、設立登記法人の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。個人番号とは異なり、利用範囲の制約はありません。16年1月以降の税分野での手続きからの利用が想定されており、法人税申告の場合、16年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになります。
※法人番号はインターネットを通じて公表される予定です。
 ■事業者におけるマイナンバーの利用場面
■事業者におけるマイナンバーの利用場面
| 社会保障分野 ※別表第一 |
●個人番号利用事務実施者としてのもの
(1)健康保険組合の実施する事務
(2)企業年金の実施主体が実施する事務 |
●個人番号関係事務実施者としてのもの
健康保険、雇用保険、年金などの場面で提出を要する書面に従業員等の個人番号を記載。 |
| 税分野 ※一般の民間企業(非金融機関)の場合 |
●個人番号関係事務実施者としてのもの
税務署に提出する法定調書等に従業員や株主等の個人番号を記載。 |
マイナンバー対応ロードマップ例
2015年10月にマイナンバーの付番・通知がスタートします。16年1月の利用開始まで、企業ではどのような対応準備が必要なのでしょうか。スケジュールを確認しながら、想定される業務をまとめました。利用が始まるまで1年以上ありますが、早めの準備が確実な実施につながります。マイナンバーに関する最新情報は、
内閣官房の特設サイト
をご確認ください。

抜け・漏れなく確実に遂行したい
人事労務業務
労働安全衛生法改正
近年の社会情勢の変化や、労働災害の動向を背景に、労働者の安全と健康の確保対策を充実させるため、2014年6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が施行されました。改正項目は全部で7項目あり、14年中から16年6月までの間に順次施行される予定です。総務業務に直結する改正となるので、該当する場合はしっかりと改正内容を把握し、対策準備を進めておきましょう。なお、施行日については、今後政令で規定されます。
企業の大半が対象となるストレスチェック
7項目ある労働安全衛生法の改正のうち、ほとんどの企業が該当するのが「ストレスチェックの実施等が義務化」です。義務化された背景には、職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移していること、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど(2009年度:234件、2010年度:308件、2011年度:325件、2012年度:475件)が挙げられます。今やメンタルヘルスは、企業にとって取り組むべき対策の上位項目に位置づけされます。ストレスチェックの実施等の義務化の内容を確認してみましょう。
◎常時使用する労働者に対して、医師、保健師等(※1)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)(※2)を実施することが事業者の義務となります。ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。
※1:ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。
※2:検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。
◎検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
◎検査の結果、一定の要件(※3)に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
※3:要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。
◎面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置(※4)を講じることが事業者の義務となります。
※4:就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うこと。
| 改正項目
|
(1)化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務化
施行日:2016年6月までに施行予定 |
(2)ストレスチェックの実施等が義務化
施行日:2015年12月に施行 |
(3)受動喫煙防止措置が努力義務に
施行日:2015年6月までに施行予定 |
(4)重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度導入
施行日:2015年6月までに施行予定 |
(5)法第88条第1項の届出廃止
施行日:2014年12月までに施行予定
規模の大きい工場等(※)で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出が廃止されます。
※届出が義務付けられていたのは、製造業(一部除外)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業であって、電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上の事業場。
|
(6)電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定、譲渡制限の対象に
施行日:2014年12月までに施行予定 |
(7)外国に立地する機関も検査・検定機関として登録可能に
施行日:2015年6月までに施行予定 |
事業者には、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、ストレスチェックの実施が義務づけられます。また、ストレスチェックを実施した後、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師の面接指導を実施し、必要な場合は、作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な就業上の措置を講じなければなりません。ストレスチェック制度の目的は、(1)労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、(2)労働者自身のストレスへの気づきを促す、(3)ストレスの原因となる職場環境の改善です。ストレスチェックの項目については、厚生労働省で専門検討会が開かれている最中ですので、動向をチェックしておくと同時に、産業医や社労士との連携強化が求められます。今後、フレックスタイム制やワークライフバランス向上のための法改正も検討されているので、人事労務管理の変化に対応できるよう、システムの確認をこまめに行うことも重要です。
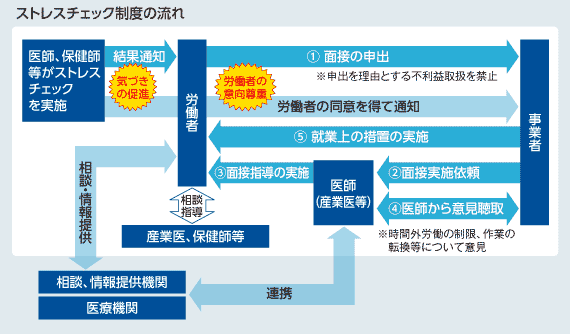
ストレスチェックの実施等については
産業保健総合支援センター
(全国47か所)の活用を!
タレントマネジメントとは?
タレントマネジメントとは、自社の人材(=タレント)が、どのような能力やスキルを持っているかを把握し、その力を最大限に引き出すために、配置や教育、投資などを行うこと(=マネジメント)です。有能な人材を確保し、適切な場所で力を発揮させることは、企業の将来を左右する生命線であり、重要な経営戦略のひとつに挙げられることは間違いありません。そして、少子高齢化や働き方の多様化により、今まで以上に、企業のタレントマネジメント能力が重要視されています。
タレントマネジメントを成功させるために
優秀な人材は昨日の今日で育つわけではなく、また、たとえ優秀な人材を確保しても、その能力を発揮できるステージがなければ宝の持ち腐れになってしまいます。企業に求められるのは、人材の「適切な教育、無駄のない配属、可能性の見極め」の3つです。
1つ目の適切な教育は、業務に必要なスキルはもちろんのこと、本人がすでに持っている能力を伸ばすのか、新たな能力を身につけさせるのか、本人の意思はどうなのかといった「この人材に本当に必要な教育は何か」を考えることです。2つ目の無駄のない配属は、将来のキャリア形成も踏まえ、「どのような未来が適切なのか、どのような舞台で力を発揮するのか」を想像することです。そして、3つ目の可能性の見極めは、「今はその力がなくても、適切な教育や配属を用意することで、どのような力を発揮するか」を予想することです。この3つは、それぞれの要素が絡み合ってこそ効果が現れます。
とは言っても、口で言うほどタレントマネジメントは簡単なものではなく、効果が見えるまでには、それなりの時間がかかります。そこで活用したいのが「人材のデータ」です。人材のデータを活用すれば、人材のキャリア、特技、資格などのデータから、傾向や対策を考えることができます。ただし、データの集計・分析は、システムなくしては実行できません。タレントマネジメントと人事労務に関連する奉行シリーズの活用については、開催中の奉行フォーラムにてセミナーを行っており、専門家を招いた充実の内容となっています。皆様の業務に役立つ情報をご用意していますので、この機会にぜひご参加ください。
総務業務のトレンドに強い
奉行 i 8シリーズの対応力!!
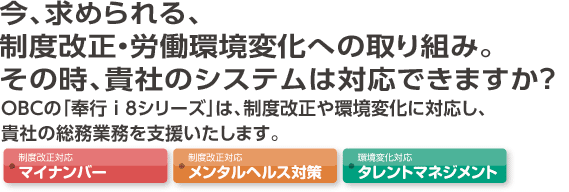
2015年10月から通知がスタートするマイナンバーについては、各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載して行政機関等に提出しなければならないため、マイナンバーの取り扱いは必至となります。どの書類に誰のマイナンバーを記載するかを把握する必要があり、業務システムの対応も万全でなくてはなりません。奉行 i 8シリーズでは、人事奉行 i 8、給与奉行 i 8、法定調書奉行 i 8がマイナンバーに対応予定です。法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできないため、システムの制御機能も活用のポイントです。また、法人番号の取り扱いも同時進行で行われるので、対応システムを準備して、しっかりと備えることが大切です。
一方、労務管理や人事に関わる対応への取り組みも求められています。2014年6月に「メンタルヘルス対策の法的義務化」が国会で可決されたほか、少子高齢化、65歳雇用義務、働き方の多様化などの労働環境変化に伴い、優秀な人材を確保し育成するための仕組みとして「タレントマネジメント」への注目も集まっています。
マイナンバーや人事労務管理など、企業に求められる総務業務が増えるなかで、業務システムの存在価値は高まっています。OBCでは奉行 i 8シリーズをはじめ、様々な場面で皆様の総務業務を支援し、安心して業務に集中できる環境をご提供します。
|
制度改正・労働環境変化は、奉行シリーズにおまかせください!
|
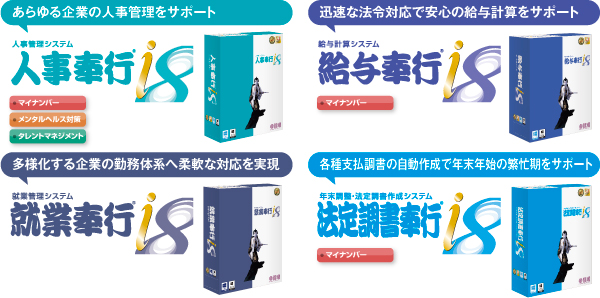 |
|
奉行フォーラム2014にて関連セミナー開催中!
2014年10月から順次全国で開催している「奉行フォーラム2014」では、人事労務管理をはじめとする総務業務や奉行 i 8シリーズ活用の関連セミナーを開催しています。専門家を招いた充実したセミナーを多数ご用意し、皆様の業務を確実に支援する情報が満載のイベントとなっています。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
| マイナンバー
|
●2016年に始まるマイナンバー制度に企業はどの様に備えるべきか
●奉行シリーズではじめるマイナンバー制度への備え |
|
労務管理・メンタルヘルス対策など
|
●「未払い残業代請求」のリスクについて、ご存じですか?会社を守るための未払い残業代請求に対する対策セミナー
●ストレスチェック法制化! 人事・総務が知っておかなければならない企業の健康リスク管理とメンタルヘルス対策とは |
|
人材育成・タレントマネジメントなど
|
●明日から実践できる!人材データを活用した人材育成法
●「人」に関わる30の総務業務を改善!システム活用による生産性アップ術 |
|
早期対応に向けた様々なご提案をご用意しております。ぜひお気軽にOBCにご相談ください。お電話、または「奉行クリック」内の製品導入に関するお問い合わせフォームをご利用ください。


●奉行EXPRESS 2014年秋号より [
→目次へ戻る
]
|