 パソコン&モバイルツールで節電
業務を遂行する上で、もはやなくてはならない存在となったパソコンとモバイルツール。「仕事のスタートはパソコンの電源を入れることから」「仕事=パソコン操作」「商談ではタブレットパソコンが必携」という方も多いのではないでしょうか。では業務中のパソコンの使用状況についてはどうでしょう。日中はほぼ電源がオンになった状態が続き、電源を切らずにそのままの状態で席を離れることも日常茶飯事ですよね。一方、モバイルツールに目を向けてみても、最近の台頭であるスマートフォンやタブレットパソコンはバッテリーの減りが早いこともあって充電頻度が高く、電力使用量は増え続けるばかりです。
パソコンやモバイルツールの一台当たりの電力使用量は大型IT機器に比べれば少量かもしれません。しかし、従業員全員が一人一台以上を当たり前のように持つ時代です。塵も積もれば山となる――。パソコンとモバイルツールの節電対策が鍵になります。
IT機器自体の節電が必須。選択条件は優秀な省電力
処理能力や操作性の向上など機器の高度化によって消費電力量が膨らむとともに、手が届きやすい安価なITツールの登場を背景に大量導入が可能となり、企業が持つIT機器の台数が増加。オフィス内の消費電力量もそれに比例して右肩上がりに増えています。これは企業がITツールを選ぶ際、節電や電力コストを考慮する上で、もはや「省電力仕様」が選択の最優先事項となる裏づけです。
では省電力仕様とはどのようなものなのでしょうか。スタンダードは「省電力モード」です。パソコンであれば、メーカーによって仕様は異なりますが、専用ボタンなどで簡単に切り替えられるのが特長で、離席などで使用しない時に液晶ディスプレイを暗くしたり、部品への給電を停止したり、人の存在の有無を感知して着席していない場合は自動で電源をオフにするなど、様々な省エネ機能を備えています。この省電力モードの活用により電力消費が通常の数十%近く下がるという結果も出ています。また、CPUやMPUなどの部品自体の省電力化も進んでいて、電子部品レベルで稼動時電力や待機電力の削減につながっています。もちろん、処理装置が高性能になれば、高度な“省エネ頭脳”を働かせることも可能で、ACアダプタからの電力供給を抑制する機能や、出荷前に業務に支障が出ない程度に「あえて処理能力を落として節電する」パソコンも登場しています。スイッチを使って簡単に給電のオンオフを操作できるコンセントや、コンセント単位で電力の使用量を見える化できるアイテムもあるので、こういった節電グッズを上手に取り入れるのも節電効果が狙えます。
一方、モバイルツールの電池を長持ちさせるには、こまめな電源オフに加え、パソコン同様に、ディスプレイの明るさを暗めにしたり、Wi-FiやGPS機能をオフにしたりする省エネモードやエコモードを活用することです。ソーラー充電器などの省エネグッズを取り入れるのも賢い方法です。
消費電力量の見える化。管理システムで常に節電
パソコンやモバイルツールを活用した節電もあります。例えば、電力消費量やIT機器の稼動状況などをインターネット経由で監視・操作するクラウド型の制御システムです。オフィスや店舗の分電基盤に電力測定器を装着し、管理装置を使って消費電力のデータを収集します。パソコンのブラウザからサーバにアクセスして遠隔から電力消費を随時把握することができ、電力の使いすぎを警告したり、使用量を分単位、時間単位などでグラフ化したり、使用量の高い順に表示するなどの分析も可能です。
また、パソコンの電力消費量を確認・監視するソフトもあります。パソコンに節電専用ソフトを取り込み、電力量を測定する仕組みで、会社全体や利用者ごとに使用量の変化を日や月単位で確認できたり、未使用時に自動的に省電力モードに切り替えたりできます。使用量のグラフ表示や削減量の料金目安を表示してくれるので、従業員の節電意識を啓蒙するツールに使えそうです。
 
モバイルツールを使えば、いつでもどこでも消費電力量や稼働状況のチェックが可能です。そればかりか、スイッチのリモコン代わりにしてIT機器の電源を遠隔操作するなど、多様な使い方が広まりつつあります。オフィス内で社員が席から離れただけで自動的に照明やパソコンの電源をオフにする、位置確認機能で着席しようとすると自動的にオンになるといったことも近い将来当たり前の光景になるかもしれません。
従業員一人ひとりの節電促進にスマートフォン向け節電アプリはいかがでしょう。SNS(交流サイト)を使った節電バトルゲームなどで楽しみながら節電に取り組めば、「節電疲れ」の心配も軽減されるかもしれません。資源エネルギー庁では「節電スマートフォンアプリ大賞」を開催して優秀なアプリを表彰しています。ぜひ、参考にしてみてください。
 ワークスタイルで節電
昨夏の電力不足は、社会全体のワークスタイルを変えるきっかけとなり、サマータイムを導入したり、電力不足に備えて節電目的で在宅勤務を採用・検討したりする企業が増えました。企業でも家庭でも外出先でもインターネットが通じ、多種多様なITサービスがリリースされている今日、自宅をオフィスに変えることに難しいことはありません。しかしながら、作業は自宅に居ながらできても、業務の開始と終了の把握や、きちんと業務に取り組んでいるかといった勤務実態の確認は容易ではなく、仕組みがしっかりしていないと現場に混乱を招きます。また、機密情報漏えいの危険や個人情報の管理問題などセキュリティ面のリスクも拭いきれません。
柔軟なワークスタイルを受け入れ、その仕組みを確立した企業は、節電だけでなく、これから問題になるであろう従業員の育児や介護の両立などのワークライフバランスへの対応力にもつながります。
節電目的の在宅ワークはITが不可欠。不安もリスクも解消する方法とは
総務省発表の在宅勤務による電力量の削減効果(試算)によると、オフィスでは、働く人が減ることで、空調、照明、複合機などのOA機器の電力が抑えられ、在宅勤務導入後にオフィスでは通常よりも43%、家庭との合算では14%の電力量を削減できるといいます(グラフ参照)。在宅ワークは柔軟な働き方の一つであると同時に、優秀な節電方法であるといえそうです。
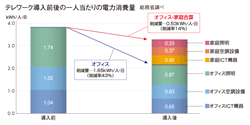
しかし、在宅ワークは単に「家での作業」ではないことを理解しなければなりません。在宅ワークはあくまで「代替オフィス」の一つであり、作業に当たるにも会社にいる時と同じように臨む必要があります。ですが、従業員側にそのような自覚があり実際にしっかり業務に励んでいても、上司や管理者は疑心暗鬼になることもあります。そこで有効なのがITを使った管理体制です。いくつか例を挙げてみましょう。
■ウェブカメラ:インターネット電話やチャットなどウェブカメラで相手と通信できる手段を使い、業務報告を行います。打ち合わせに使う、あるいは複数人での同時使用で会議を行うなどの活用方法があります。
■社内SNS:リアルタイムで情報をやり取りできるメリットをいかし、随時状況を報告。短いメッセージで完結するので、従業員の負担も確認作業の手間も軽減できます。チャット機能を活用すれば、さらに効率的です。
■GPS機能:GPS機能付きのモバイルツールで、従業員の位置情報を確認します。誰がどこにいるかを確かめられるのが特長です。 データセンター活用が節電を支える。賢い利用で電力も労力も低減する
在宅ワークで懸念されるのがセキュリティ問題です。こういった場合は、例えば、シンクライアント端末の利用が挙げられます。シンクライアント端末とは、データを残さない仕組みを備えた端末のことで、情報漏えいの回避や端末管理の負担軽減に効果を発揮するほか、記憶装置がない分、それだけ機能が絞り込まれており、電力消費量が通常のパソコンよりも少なく節電にも有効です。
セキュリティを確保するもう一つの方法に、リモートアクセスがあります。これは、インターネットを介して社内のパソコンにアクセスし、そのパソコンを目の前で操作している時と同じように利用できる仕組みです。データを残す際も社内のサーバに保存するので安心です。

節電はもちろん、在宅ワークのセキュリティにも頼れるツールがあります。それがデータセンターの活用です。近年、また昨年以降にさらに注目度が増した「クラウドコンピューティング」は、このデータセンターがあってこそ。自社のシステムをデータセンター内に構築し、自宅や外出先からインターネットを介してリモートアクセスを使い業務システムにアクセスします。これにより、オフィス以外の場所からも基幹業務ソフトなどの主要ソフトの操作が可能になります。スケジュール管理や会議機能、ファイル保存などを行うグループウェアもあります。
自社のサーバをデータセンターに預ける「ハウジングサービス」や、データセンター内のサーバに自社のシステムを移行する「ホスティングサービス」など、データセンターの活用は様々です。自社に専用のサーバルームを設置することは、場所の問題もあり、空調管理の手間もかかります。データセンターであれば建屋自体が強固な構造になっており、電源を多重化して停電時にも電源供給を維持しています。自家発電装置の備えもあり、万が一の場合にも、数時間から数日間の電力供給が可能なため、安心度もぐんと高まります。最近では、コンピュータを冷却するのに最適化した構造を採用し、高度な空調制御機器を備えて省エネ効果をいかんなく発揮しているデータセンターもあります。また、冬場は外気を活用してサーバルームを冷却する事例や、サーバの発する熱を熱源として利用する施設もあります。これだけITのプロがそろっていれば、節電ばかりでなく、災害やパンデミックなどが起こった際の事業継続の備えにも効果的です。
 オフィスで節電
平均的なオフィスビルの電力消費の内訳をみると、空調が48%、照明が24%、OA機器が16%となっており、これら三つを合計すると電力消費の約9割を占めていることになります(図参照)。このデータを踏まえ、オフィスで節電を行うにはどのような対策が考えられるのでしょうか。
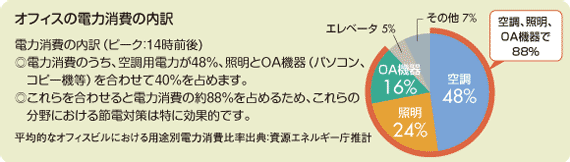
オフィスの節電が基本中の基本。こまめな見直しが実を結ぶ
オフィス照明の節電策に、使用していない会議室の電灯を消す、廊下やトイレなどの蛍光灯を間引きするなどありますが、もう一つ、蛍光灯照明からLED(発光ダイオード)への転換が挙げられます。LEDは家庭向け商品で先行していますが、オフィス向けに電磁波などのノイズを低減したものや、蛍光灯と同じ直管型の普及も進み、初期投資を抑えられるリースやレンタルによる導入も増えてきています。LEDの魅力は何と言っても長寿命と消費電力の少なさ。ある調査によると、信号機の電源を電球式からLEDに交換した際、全国で9.35億ワット時の消費電力を削減できたといいます。こうした大幅な消費電力のカットを事業所や工場、店舗などで推進する意味は大きいといえます。LEDは使用時の発熱を抑えることで、エアコンの冷房効果が大幅にアップするという報告もあります。
また、LEDと並んで注目されているのが、従来の蛍光灯照明の効果を大幅に改善した高効率照明です。高性能反射板と高効率インバーターの組み合わせで、一灯で二灯分の照明を実現した機種もあり、単純計算で消費電力を半分にカットできる効果が期待されています。
OA機器の普及もオフィスの消費電力量を押し上げている要因の一つです。省エネにはこまめな電源オフが有効ですが、機器自体の省電力化も無視できません。OA機器の内訳ではパソコンの台数が圧倒的で、電力の消費量の大半を占めていますが、複合機やプリンタなどの印刷用機器も意外と電力を使っています。種類によって異なりますが、複合機はトナーを紙に定着させる装置の過熱などに電子レンジ並みの電力を使うことをご存知ですか。素早く印刷するために予熱しておく必要があるので、待機時にも電力を使っています。これらの消費電力を低減させるには、省電力モードに素早く移行したり、転写レーザーをLEDにしたりするなどの技術を用いた製品を選択肢に入れておきたいところです。
インクジェット方式の印刷用機器を選ぶことも賢い方法です。インクジェット方式はレーザー方式に比べて1〜2割程度の消費電力になるため、電力使用量を抑えられます。製品が充実してきたからこそ、節電のための賢い使い分けができるのです。

空調、とりわけエアコンの省エネは、燃費の悪いエアコン自体を取り換える大幅な工事や、エアコンの制御システムでの集中管理が考えられます。しかし、多額の費用がかかったり、制御されることで業務に支障をきたしたりする恐れもあります。このような場合は、マンパワーを駆使し、席の配置を分散させずに一カ所に集めて一部のエアコンのスイッチを切る、夏場であればクールビズを採用し、太陽光の当たらない場所に席を移す、逆に冬場は太陽光のあたる場所に移るなどのアイデアを採り入れたいですね。最近では、コンセントで電力管理ができる技術も開発されているので、そのような製品の導入も検討も効果的です。
リスクに備える頼れる機器が必需? 電力の源を確保する注目のアイテム
電力不足問題の長期化が予想される中、停電への備えとしてエネルギー関連機器やバックアップ電源装置にも注目が集まっています。非常時の電力供給には大きく分けて二つあります。一つ目が「貯めていた電力を使う」、二つ目が「発電して電力を使う」です。
前者で一般的なのが蓄電池です。従来はハイブリッド車や電気自動車向けの車載用にほぼ限定されましたが、電力供給に対する不安が広がるにつれ、オフィス用や家庭用の製品も発売されるようになりました。夜間に電力を貯めるタイプ、発電した電力を貯めるタイプなど種類は様々あります。最近は小規模オフィス向けに机の下にしまえる小型業務用蓄電池や、数時間の停電中にも十分な業務を継続できる安価なものも登場しています。
後者は、主に大規模オフィスや工場などでの引き合いが多いといわれる自家発電機です。発電用燃料には重油や液化天然ガスなどが使われます。最近は環境に配慮した太陽光発電、小水力発電、小型風力発電などのエコロジー発電にも注目が集まっています。
 サーバで節電
リスク分散や設備の省エネ化のため、データセンターにデータやシステムを移行したり、サーバそのものをデータセンターに預けて保管したりするケースが増えています。その需要に伴い、国内外でデータセンターの新設・増設ラッシュが続いています。
データセンターはIT機器の稼働以外に、必要な電力のほとんどを空調が占めています。そのため、省エネタイプの空調を導入する、あるいは集中型の冷却システムを採用して効率を上げる、また給電システムを刷新して電気供給量を減らすなどの対策が取られていますが、これは自社でサーバの節電を行う際も同様で、いかに空調の電力を抑えるかがポイントです。省電力型の電子部品を使用した製品を選択し、365日24時間稼働し続けるサーバのコストを下げるとともに、遠隔操作や管理機能などのサーバの利点をいかした節電方法を考える必要がありそうです。
節電の可能性を最大限に引き出す。オフィスの必需品・サーバの魅力
サーバの節電には二通りの方法があります。一つが「サーバ自体の節電を行うこと」、もう一つが「サーバを使って節電対策に取り組むこと」です。それぞれの特長を挙げてみましょう。
【サーバ自体の節電】
●省エネ化された部品を搭載した製品を選ぶ
休みなく稼働するサーバは、こまめなスイッチオフが難しい製品です。そのため、サーバ自体の節電を行うためには、省電力化された部品搭載の製品を選ぶことが求められます。省電力型のCPUやハードディスクドライブ、効率のよい冷却装置、小規模オフィスであれば業務に合わせて小型モデルを選ぶのも一つの手です。稼働率が下がる夜間などに自動的に給電を抑える機能のサーバも有効です。
●ハウジングサービスを利用する
ハウジングサービスとは、自社が持つサーバをデータセンターに預けて運用を任せることです。インターネットなどのネットワークを通じて自社からデータセンターにアクセスし、そこからアプリケーションを利用したり、保存情報を閲覧したり、データを保存したりします。自社で運用する手間が省け、その分のコスト、電力、スペースを削減できます。昨年はオフィス倒壊のリスクヘッジ、代替オフィスへの移行や在宅ワークの需要から、自社にあるサーバの引っ越しが相次ぎました。堅牢な建屋、効率性を高めた設備、セキュアな管理体制、ITのプロによるアドバイスなど様々なメリットがあるため、ハウジングサービスを検討する企業も増えています。
●仮想化サーバに集約してサーバの台数を減らす
仮想化とは、専用ソフトを使って一台のサーバを複数台あるかのように分散して使うことです。一台のサーバで別々のアプリケーションを動かしたり、異なる企業が一台のサーバを共同利用できたりします。例えば、現状のオフィスで、会計や顧客管理などの基幹業務サーバ、メールサーバ、ファイルサーバなど計三台のサーバを利用していたとします。仮想化システムの利用ならば、これを一台に統合することが可能になります。こうなれば、節電はもちろん、サーバ二台分のスペースが空き、運用コストも減らすことができます。
【サーバを使った節電対策】
●社内の節電状況を監視・制御・忠告する
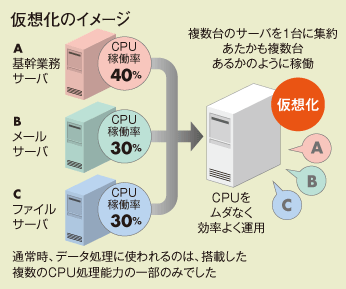
サーバの優れた点は、社内全体のIT機器を一括管理し、管理者権限で制御・監視などを行えることにあります。例えば、パソコンやプリンタなどの情報機器の稼働状況を監視し、電気使用量の通知に加え、稼働していない機器の電源を遠隔操作で切断したり、サーバの消費電力の監視機能を行うこともできます。最近では、コンセントとサーバの間に監視機器を設置し、設定値以上に電力を使っている場合には、管理者にメールで警告するといったサービスもあります。消費電力量を部署単位や期間単位で把握できるため、企業の節電計画立案に役立つと期待されています。

昨夏はオイルショックぶりに電力使用制限例が発令され、社会全体に衝撃や混乱を与え、「でんき予報」を確認して電気需要状況を知って行動するパターンが日常化しました。今もなお予断を許さない状況の中で、節電行動はもはや一時の緊急体制でも節電努力でもなく、体質化しなければならないといっても過言ではありません。
当たり前のことですが、企業を支えるコンピュータシステムの稼動には、電力が不可欠です。現在の業務を手作業に切り替えることは不可能と言ってもいいくらいです。もしも電力供給がストップしたら…。今行っている作業のほとんどは継続できないでしょう。「私たちが電力を抑えても微々たるものでは?」と思うかもしれませんが、その微々たる量こそ、電力を消費している源です。
節電の効果は電力を抑えることだけではありません。省電力化によって電気料金のコストは下がり、電力を無駄遣いしない働き方は無駄なプロセスを省いて効率化を促し、節電を目的とした柔軟な働き方は自然災害などで供給インフラが寸断された場合の対応力を向上させBCPに貢献します。
節電の効果を最大限に発揮するにはITの力が不可欠です。「IT機器を増やしたら、消費電力量が増える」とは決して断言できません。近年発売されている製品は省電力に優れたものも多く、むしろ買い替えによって節電が進みます。
節電ITサービスも選択肢の幅が増えています。自社に合ったITツールを取り入れることで、節電そのものの効果、そして節電に伴う業務への効果を得ることができるはずです。
|