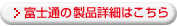処理能力の高いパソコンの登場で業務に変化
動画やインターネットを使ったサービスで使える機能も拡大 |
近年発売されているパソコンのほとんどは、どれもスペックのよい部品を搭載していて、たとえ前シーズンモデルでも、その性能は数年前のパソコンに比べ格段に高まっています。特に昨今登場したパソコンの優れた点といえば、その処理能力の高さです。処理能力向上のおかげで、今までパソコンユーザーのほとんどがストレスを感じていた「パソコンを立ち上げる時間」「エクセルやワードなどのアプリケーションを開く速さ」「容量の多い画像や動画の処理スピード」などの“イライラ”が劇的に解消されました。また、ディスプレイ画面は鮮やかに、そして滑らかになり、視覚的なストレスも軽減されています。
このように、パソコンの性能やデータ処理能力が高くなると、改善されるだけでは業務作業のスピードや作業環境のストレス軽減だけではありません。仕事に使えるさまざまな“+α”機能が増えてきます。特に今注目のコンテンツと言えば「動画」です。
例えば、商談のプレゼンテーション時、顧客に会社案内や商品カタログを見せながら説明したいとき、接客マニュアルや研修テキストで実際に動作をしていることころを盛り込みたいとき、動画を活用したいと思ったことはありませんか。今は、デジタルカメラでも簡単にきれいなムービー撮影ができます。こういった動画撮影機能を活用すれば、ビジネスの可能性ももっと多様になるはずです。
しかし、この使える動画、テキストファイルやJPEGファイルと違って容量が多く、処理能力が低いパソコンだと、その重さに耐えられずにフリーズしたり、次の動作に移るまでに何分もかかったりするなど思うように作業が進みません。動画コンテンツがサービスの中心になる中で、処理能力の高いパソコンへの買い替えも検討すべきかもしれません。
ビジネスシーンでは「ITツールをいかに活用するか」が課題です。そして、その中心となるのはやはりパソコンです。先ほど動画というキーワードを挙げましたが、現在、インターネット経由のテレビ会議やビデオチャットなどの映像を活用もビジネスでは当たり前になってきています。これらは当初、出張費削減や効率化といった効果を目的としていましたが、今は新たにテレワーク(在宅勤務)や省エネ対策として使われるようにもなりました。ITの変化に対応する要はパソコンです。改めて見直してみてはいかがでしょうか。
 |
いつでもどこでもパソコン1つで仕事が可能。ネットワーク活用で仕事を止めない
|
|
通信回線が安定しているインターネットの活用は、BCP策定には不可欠です。特定のデスクを持たない「アドレスフリー」に代表されるように、パソコン+インターネットがあれば、場所を選ばず大体の仕事はできることは周知の事実。これはつまり、いつでもどこでも、たとえ遠隔地にいても仕事が継続できる証明です。インターネット電話やビデオチャットを上手く取り入れるのも有効手段です。また、この仕組みを使えば、介護や育児のために会社を辞めざるを得なかった従業員に、テレワークを提案して業務を継続してもらうこともできそうです。今夏の節電では、在宅勤務を推奨したり、サマータイム制を導入したりする企業も見受けられます。これは、パソコンとインターネットで新しい働き方を見つけるよい機会です。USBキーを使って、ファイルのダウンロードや印刷に制限をかけてセキュリティを保ち、社内にいるときと同じ環境を作り出すサービスも出ています。BCPを通じて、リスクだけでなく新たなメリットの発見にも期待がかかっています。 |

|
省エネ機能でこまめに節電。使用頻度が高いからこそ消費電力を最大限抑えたい
|
| 業務のパートナーであるパソコンは、電力消費の身近な代表格。今夏の節電ポイントは、「昼間のピーク時の使用電力をどこまで減らせるか」です。やみくもに「電源を消せ!」といっても、節電意識は浸透しませんし、業務遂行にストレスが溜まる一方です。そこで、業務に支障をきたさない節電機能をピックアップしてみました。
|
節電ボタン |
ボタンを押せば瞬時に標準モードから節電モードに。画面の明るさやスピーカーの音量などのパソコンデバイスの調節を行います。節電モードのユーティリティで設定を変えられるので、仕事内容に合わせて調整できます。バッテリーユーティリティで充電量を下げるのもエコ。10〜30%の省エネが見込めます。 |
深夜充電 |
ノートパソコンのバッテリーを電力消費量の少ない深夜に充電し、そのバッテリーを昼間に使う仕組み。昼間はバッテリーだけでパソコンを稼働させるので、外部電力の供給が不要。ACアダプターからの電力供給を制御する設定も有効です。 |
人感センサー |
利用者の不在を自動で認識し、パソコンが勝手に節電モードや電源オフになってくれるセンサー。離席中の電力の無駄を省けます。 |
省エネプロセッサー |
パソコンの心臓部と言われるプロセッサーの処理能力を落として省エネします。処理能力の向上に比例して消費電力量も上昇したプロセッサーを、例えば文章と表計算の作成だけに機能を限定する設定に切り替えて、あえて「後退」させることで節電。旧製品に比べ、消費電力を約60%抑えられたという結果も出ています。 |
|

|
「治療」より「予防」。猛威を振るう脅威に立ち向かう万全の備えを日頃から
|
USBメモリーなど外部メディアを通じてウイルスに感染する「オートラン」をはじめ、迷惑メールを送りつけてウイルス付の添付ファイルを開かせたり、URLを張り付けて悪質なウェブサイトに誘導したりするなど、ウイルスの脅威は後を絶ちません。最近では、偽のセキュリティソフトをダウンロードさせ感染してしまうケースも見受けられます。
管理職や営業担当者など名刺交換を頻繁にする人は、仕事の依頼を装ったメールや、知人の会社名を偽った差出人からのメールを開いてしまうこともあり、知らない間に感染が広がっていることも懸念されます。一方で、ITの高度化により個人から特定の企業を狙った嫌がらせも横行しています。不正アクセスによるウェブ改ざんで、個人情報や機密情報が流出すれば損害もひどく、信頼低下は避けられません。最悪の事態を防ぐためにも、日頃からの対策が肝心です。 |
セキュリティ対策ポイント
1 |
最新のウイルス情報をチェックし、ウイルススキャンやアップデートを欠かさない
|
2 |
不要なデータはパソコンから削除する(データの取り扱い・削除方法にも注意) |
3 |
遠隔地からの接続ではセキュリティを確保する |
4 |
外部のLANを使用する場合は、IPアドレスやネットワークを限定する |
5 |
プロバイダーやセキュリティソフトベンダーにセキュリティ対策のアドバイスをもらう |
|
| 知っておきたい単語集 |
動画投稿サイト |
利用者が投稿した動画を利用者同士で共有するサイト。独自の番組を放送することもあり、エンターテイメントとして楽しむ人も増えています。 |
インターネット電話(音声通信) |
インターネット回線を利用したパソコン同士の電話。活用する企業も増加中。 |
ビデオチャット |
ウェブカメラを使いリアルタイムで動画を送り合う、いわばインターネットを使ったテレビ電話。複数利用が可能なサービスであれば、コストを抑えた本社−支店間や本社(日本)−支社(海外)間の会議などにも活用できます。 |
ユニファイドコミュニケーション |
テレビ/ウェブ会議、固定/携帯電話、FAX、メール、多機能携帯端末、SNS(交流サイト)などのコミュニケーションツールを統合管理すること。分散するツールを統合することで、効率性・機能性・生産性を高める目的があります。 |
モバイルの主流はタブレット端末に
未知数の可能性を秘めたツールをビジネスにも応用 |
ノートパソコンはタブレットパソコンに、携帯電話はスマートフォンに、ビジネス雑誌は電子書籍に――。
携帯電話に代表されるインターネット通信可能なモバイルツールは、今や一人一台以上が当たり前の時代。機器自体の価格が低下し、求めやすくなったことに加え、データ通信料金の改定や、安価な料金プランなども登場し、個人ユーザー以外の企業も、法人契約で営業部の社員全員に端末を持たせるなど、営業支援ツールとして有効的に使われるようになりました。
そして近年、このモバイルツールに新たに“高機能”がプラスオンされました。その代表が、タブレット端末のスマートフォン、タブレットパソコン、電子書籍です。指を滑らせたり叩いたりするタッチパネルを採用しているので、操作も簡単で使いやすく、すぐに使いこなせるようになるのも普及拡大に貢献しています。機能面では、従来のモバイルツール同様、営業支援ツールや経営動向のリアルタイムチェック、在庫確認・発注はもちろん、車のキーロックや入退室管理承認キーなど、機器自体が新たな“もの”に変化するシステムに進化しました。
高機能モバイルツールが市場に出回ったことを背景に、これらを活用する企業も増えています。では、これらのツールはビジネスシーンでどのような効果を発揮するのでしょうか。
1つ目の効果は「販促活動・新規開拓」です。商品宣伝やマーケティング活動に活用できます。例えば、新作衣料品の商談時、重いカタログや写真集を持ち歩く替わりに、タブレットパソコンにそれらのデータを入れ、顧客に画面を見せながら説明していくのはどうでしょう。指で操作しながら拡大したり縮小したりすれば、細部の素材感も全体のスタイルも確認できます。着せ替え機能などがあれば、コーディネート提案も瞬時に表示。インターネットで在庫の確認ができる仕組みを使って、その場で発注して決済することも可能になります。
2つ目の効果は「サービス」です。B to B/B to Cの双方で、流通チャネルの開拓や強化、コンテンツの充実などが期待されています。高機能モバイルツールでは、高画質で容量の重い画像や動画でもストレスなく閲覧できるのが魅力で、その特性を活かしたサービスも考えられます。
そして3つ目の効果が、「管理システム」です。今までも、モバイルツールを使った情報共有システム、営業支援ツール、生産性向上サービスなどの管理システムがありましたが、高機能モバイルツールに替わると、これらのシステムを“攻め”の姿勢で活用できるようになります。
システムに合わせて働き方を変えるのではなく、自社の思い描くスタイルにシステムやサービスを載せていく――。企業を成長させる要素は無限に広がっています。
 |
SNSやミニブログを活用して従業員の状況を確認
|
|
災害時などは、電話回線が制限されたり、込み合っていたりすることが多く、固定電話・携帯電話共につながりにくい状態が続きます。一方で、「電話は通じないけれど、インターネットはつながった」というように、インターネット通信は多くの人が一斉に使用しても、パンクすることはほとんどありません。その特性をBCPにいかして、従業員の安否確認にSNSやミニブログを取り入れるのはどうでしょう。今回フォーカスした高機能モバイルツールは、これらのサービス利用を前提にしているので、使い勝手もよいのが特徴です。「大丈夫」「部署全員無事」「オフィスに異常なし」など短いメッセージで簡単に素早く連絡を取り合えますし、同じサイトを閲覧していれば社内情報も共有できます。小型のモバイルツールですから、持ち出すにもかさばらず、移動しながらの操作も楽にできます。BCPには、緊急時の連絡手段として、このような手段を使ったやり取りを明記しておくとよいでしょう。
|

|
外部電源に頼らない充電グッズで楽しく節電〜携帯電話・スマートフォン対応グッズ〜
|
|
家電量販店で『補助充電器』の看板を見かけるようになり、外部電源を使わない手軽に持ち運べる補助充電装置が登場しています。出張や旅行時にも便利なこのアイテム、「停電なのに電池の残量がわずか…」といった電池切れ危機の回避に取り入れたいグッズです。
|
燃料電池 |
水と水素を発生させて燃料を起こすタイプや、メタノールを利用したタイプなどがあります。世界では、砂糖(ブドウ糖)や微生物から燃料を作る研究も進んでいます。 |
大容量バッテリー |
乾電池やコンセントからあらかじめ電気をためておく携帯型バッテリーが、小型化&大容量化を実現。 |
太陽電池 |
節電対策が進む中で、より効率的にエネルギーを蓄積できるソーラーパネルが出てきています。晴れの日が続く夏に最適です。 |
手回し型電池 |
手回し部分を回して発電します。ライトやラジオとセットになったタイプもあるので、目的に合わせて用意しておくと便利です。 |
|

|
ITの主流になり、狙われる標的に浮上中
|
高機能モバイルツールが主流になるにつれ、情報を盗み取るターゲットにも浮上してきました。今はまだ、パソコンに比べてウイルスの報告件数は少ないものの、今後悪質なウイルスが蔓延する可能性がかなりあります。銀行振り込みを行ったり、インターネットショッピングでクレジット番号を入力したり、売上情報を入力したり、名刺情報を保存すると同時に個人情報を書き足したり、便利な反面、重要な情報を取り扱う頻度も高まっています。
また、アプリケーションのダウンロードが基本のスマートフォンでは、知らないうちに悪質なアプリケーションをインストールしてしまうケースも想定されます。セキュリティソフトをインストールする、社内で操作についてのガイドラインを作るなどの対策が必要です。パソコンと同様、迷惑メール多い場合は、受信拒否の設定をし、怪しいURLは開かないなどセキュリティに対する意識を徹底したいところです。
|
| 知っておきたい単語集 |
SNS(交流サイト) |
ソーシャル・ネットワーキング・サービスと呼ばれるサービス。世界最大の会員数を誇るSNS「Facebook(フェイスブック)」のユーザー数は、なんと数億人以上。プロフィール公開、ブログ(日記)公開、チャット、コミュニティ機能があり、名刺代わりにするビジネスパーソンも。公式アカウントを設ける企業も多く、顧客への新たなプロモーションツールになっています。 |
ミニブログ |
身近な文章で、まるでつぶやくように書き込む日記のこと。利用者の文章にコメントを書き込め、利用者同士のコミュニケーションを図れるのも魅力です。 |
業務が変わる、サーバーで変える
賢い司令塔は「業務を止めない・止まらせない」が基本 |
サーバーのメリットで挙げられる点は、優れた管理力ではないでしょうか。前述のとおり、ITツールの使用頻度は日に日に増して、取り扱うアプリケーションや、蓄積する情報量も膨大になってきています。ITツールは確かに便利な道具です。ですが、一過性がなかったり、社員がバラバラに使用していたりすると、せっかくのデータも共有できず、単なる「面倒な道具」に終わってしまいます。そこでお勧めしたいのが、管理を得意とするサーバーです。サーバーはいわばネットワーク上の共通オフィスのようなもので、LAN経由でパソコンとサーバーとつながっていれば、1台のプリンターをみんなで使用したり(プリントサーバー)、共有フォルダでファイルを閲覧しあったり(ファイルサーバー)、ウェブカメラや光学ドライブなどのUSB機器を共同で使用したり(デバイスサーバー)、表計算ソフトや画像編集ソフトなどネットワーク対応版のアプリケーションを共同で使ったり(アプリケーションサーバー)、さまざまな使い方ができます。サーバーを使えば、いちいちプリンターのあるところまで行ってパソコンを接続する必要も、わざわざデータを移し替えて共有パソコンに保存する面倒もありません。近年は、1台のサーバーをあたかも複数台で運用しているような「仮想化」も取り入れられ、サーバー自体の効率化・低コスト運用・省エネの精度も向上しています。サーバーの役割はもちろん効率化の面も大きいのですが、「業務を止めない・止まらせない」という役割も担っています。運用管理ツールを用いれば、社員のパソコンログや不正アクセスやウイルスのチェック、消費電力量などを一元管理できます。
 |
業務を継続するための事前の備えをサーバーで
|
BCPの要となる情報システムの停止をどう防ぐか、その課題を情報システムの中枢を担うサーバーでどう継続していくか。これが、サーバーにおけるBCPの前提です。いくつかチェックポイントはありますが、まずハード面を見てみましょう。
サーバーは、強固な堅牢性が保たれているとはいえ、何かの原因で故障が起きる可能性はゼロではありません。部品の交換が必要になった場合、サプライチェーンから安定的に部品が供給されるか、その調達にどのくらいの時間がかかるのかを把握しておきます。電力不足回避のために、代替オフィスへの移動を検討している企業もあるでしょう。サーバーにどんな情報を保存しておけばよいのか、サーバーを使ってどのように情報を共有すればよいのかなどを取り決めておくのが賢明です。
|

|
24時間365日稼働のサーバーは節電必至。省エネ対応モデルをチェック
|
常に稼働するサーバーの節電は必須の課題。こまめに電源を落とすことができないため、省エネ機能を搭載したモデルを選ぶことをお勧めします。また、エアコンの温度設定が制限されることも想定し、冷却システムや耐熱なども考慮に入れておきましょう。
サーバー自体の省エネに取り組むと同時に、一元管理できる節電システムを導入して消費電力量の状況を把握し、節電プランの策定や機器の遠隔制御なども賢い策です。節電によるオフィス移動の可能性がある企業では、移動後の運用プランの制作も必要です。
|

|
優れた管理機能で社内外のリスクを監視
|
サーバーで情報を管理する場合はデータを暗号化して保存する、サーバーをインターネットから切り離して外部からの侵入をシャットアウトする、重要データにはパスワードをかけたり、閲覧者を制限したりする設定を行うなどのセキュリティ対策が賢明です。社員のログイン状況を記録して、ネットワークを管理することも有効です。
サーバーベンダー各社では、セキュリティ対策のソリューション提供やシステム構築サービスを行っているので、それらを活用するのも得策です。
|
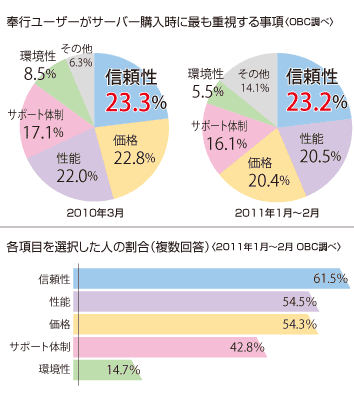
24時間365日稼働するサーバーは「止まらない」が基本で、これを裏付けるのはサーバーの「信頼性」です。OBCが行った奉行ユーザーのサーバー購入時に最も重視する事項(図参照)でも、選定条件の第一位に信頼性が選ばれています。その目利き役の奉行ユーザーから5年連続No.1サーバーに選ばれているのが、富士通のPCサーバ「PRIMERGY(プライマジー)」。多彩なシステム開発の経験と技術力を活かした高信頼の富士通品質が魅力です。特に、高・低温ランニング試験、落下試験、電波障害テスト、振動試験、擬似障害テスト、経年変化試験など、オフィスで起こるあらゆるリスクを突破して出荷されているため、安心して導入・運用が可能です。信頼を生み出す厳しい品質管理から誕生した富士通PCサーバは、まさに業務を止めない企業の最良なパートナーと言えます。
 ●富士通の高い信頼性・品質の追求
(1)部品品質
●富士通の高い信頼性・品質の追求
(1)部品品質:部品選定から高い品質を追求、サプライヤーの内部まで踏み込み、購入品の高品質を確保
(2)製造品質:サプライヤーからの納入品不良を防ぐ万全な受入検査体制、組立部材の検査、組立後の基本検査等によるお客様構成での品質確保
(3)製品品質:厳しい社内基準に基づいたシステム試験の実施
企業を取り巻く環境や意識が変化する中で、ITの真価が問われています。ITを活用してどれだけ業務を安定させられるか、それを乗り越えて成長し飛躍できるか――。ITのさらなる強化が求められています。