|
VMware、XenServer、Hyper-V――。ここ数年、サーバーを仮想化するための基本ソフトウェアが出揃ってきました。「サーバーの仮想化」とは、1台のサーバー上で複数のOSや業務アプリケーションを動かせるようにする技術のこと。サーバーの使用率を高めてITコストを削減できるほか、サーバー統合、業務継続性(BC)と災害復旧(DR)、テスト環境の構築、以前から使ってきた業務システムの延命などを実現するためのIT基盤としても威力を発揮します。また、このような潮流を受けて、サーバーの世界でも仮想化への対応をうたう製品が次々と登場。企業の業務ニーズに合わせて、さまざまな方式のサーバーを選べるようになりました。そうした中、中堅・成長企業の業務システムを仮想化するためのサーバーとして注目を集めているのが「ブレードサーバー」です。
情報システムの規模拡大につれて、サーバーの台数増と分散化が進む
ビジネスの拡大と企業の成長につれて、情報システムの規模はどんどん大きくなっていくものです。最初は1台のスタンドアローンPCから始めたものがサーバーでの処理へと移行し、やがては数台から数十台のサーバーから成る大型の情報システムへと成長していくことも、それほど珍しいことではありません。
ただ、サーバーの台数が増え、設置場所が広範囲に分散していくにしたがって、マイナス面も目立つようになります。
例えば、業務ごとに別々のサーバーを用意するやり方では、繁忙期が業務によって異なるため、「遊んでいる」サーバーがどうしても生じてしまいます。場合によっては、一月に一回、数時間しか使われないサーバーとなってしまうかもしれません。
また、別のフロアーやビル、遠隔地の支店や営業所などにサーバーを分散配備すると、プリンターやネットワーク設備などの周辺機器を共用することは不可能になります。重複投資になると分かっていても、それぞれの設置場所ごとに周辺機器を導入していかなければならないのです。
さらに、管理のための時間も必要になります。すべてのサーバーがきちんと動作しているかを確かめるために、他の作業を止めて確認をしなければなりませんし、サーバーの台数に比例してソフトウェアのインストールやアップグレードの手間は増えていきます。パッチ適用などのセキュリティ対策も、サーバーの台数が増えれば増えるほどめんどうになってきます。
1台のサーバー上で複数のOSを動作させる仮想化に注目が集まる
情報システムの規模拡大にともなって生じるこれらの問題を解決するための技術の一つとして、今、「サーバーの仮想化」が注目を集めています。本来の仮想化には「分割」「集約」「エミュレーション」などの機能が含まれますが、サーバーの仮想化でおもに行われるのは「分割」によって1台のサーバー上で複数のOSや業務アプリケーションを動作させること。例をあげると、従来は別々のサーバー(2台)及び別々のOSを使用していた「奉行製品」と「販売管理用のアプリケーション」を1台のサーバーに収めて使用するということです。この時にサーバーの中には「奉行製品」と「販売管理用のアプリケーション」と、それぞれに対応した2つのOSが存在していることになります。また、1台のサーバーではなく、一つの筐体(ケース)に収められた複数のサーバーで複数のOS/業務アプリケーションを動作させる使い方も、サーバー仮想化と呼ぶこともあります(グリッドと呼ぶ場合もあります)。(図1)
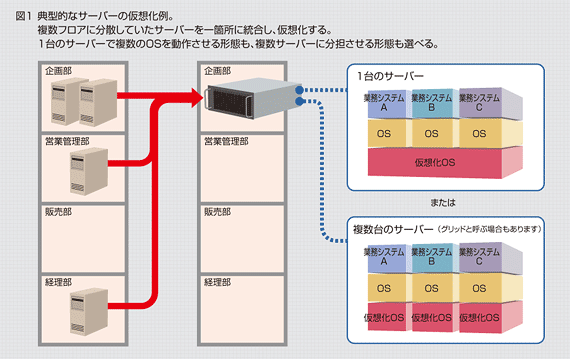
このようにサーバー仮想化が注目される背景には、仮想化OSと呼ばれる基本ソフトウェアが出揃ってきたことがあります。現時点でサーバーの仮想化に利用できるおもな仮想OSは、VMware(ヴイエムウェア株式会社)、XenServer(シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社)、Hyper-V(マイクロソフト株式会社)の3製品。いずれも、「複数のWindows Server」または「複数のWindows Serverと複数のLinux」を1台のサーバー上で動作させることができます。
この中でも、2008年7月に正式版がリリースされたHyper-VはWindows Server 2008の事実上の標準機能となっており、中堅・成長企業の間で特に人気の高い製品です。
また、Hyper-Vは「奉行シリーズ」の動作対応を正式にサポートしている仮想OSです。「奉行シリーズ」への仮想化についても、スムーズに移行することができます。
サーバー使用率を高め、浮いたコストを戦略的投資に振り向ける
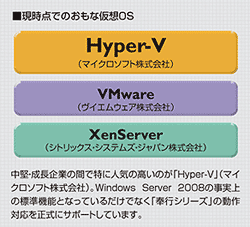
では、サーバーの仮想化に取り組むことによって、企業はどのようなメリットを手にすることができるのでしょうか。
中堅・成長企業にとっての最大のメリットは、以前から使ってきた業務システムの延命にもサーバーの仮想化は役立ちます。古いバージョンのOSを前提とする業務システムが企業内に残っている場合、そのOSが動作するサーバーがもう販売されていないという理由でサーバーの買い換えができなくなってしまうことがあります。そのような場合も、サーバーの仮想化を利用すれば、新旧両バージョンのOSを同時に動作させることが可能。最新の高性能サーバーの上で、以前から使ってきた業務システムを稼働させることができるのです。
また、経営者視点での最大のメリットとしては、サーバーの使用率が高まることによるコスト削減でしょう。

繁忙期の異なる複数の業務をうまく組み合わせて仮想化すれば、サーバーの使用率を現状の倍以上にするのは容易。サーバーの台数を減らすことによって導入コストを削減できますし、プリンターやネットワーク機器などの導入コスト、電気代、設置場所の地代家賃、管理者の人件費なども低く抑えることができます。こうして浮いたコストは、企業の競争力を高めるための戦略的投資に振り向けることが可能です。
このほか、予備の業務サーバーをサーバー仮想化で作り出しておけば、業務継続性(BC)や災害復旧(DR)への対応も万全。さまざまなトラブルや災害に遭遇したとしても、ビジネスチャンスを逃してしまうおそれはありません。また、システム開発の立場からはテスト用のサーバーを購入する必要がなくなること、経営の観点からは、サーバーを集中配備することによって監視の目が行き届きやすくなり、内部統制の確立が容易になることも重要なメリットとなります。
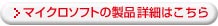
サーバー仮想化で消費電力を抑えグリーンITの実現で社会貢献を!
さらに、サーバーの仮想化は「グリーンIT」を実現するための手段としても重要な意味を持っています。
グリーンITとは、IT機器によって消費される電力を減らすなどの対策によって、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを削減する取り組みのこと。サーバーなどのIT機器は電力によって動作しており、その電力は温室効果ガス(CO2)を排出する火力発電所によって作られています。ある調査によれば、2025年にはIT機器によって消費される電力は現在の5倍にも達するとのこと。京都議定書や地球温暖化対策推進法の温室効果ガス削減目標を達成するには、IT機器を利用する企業にも応分の努力が求められているのです。
サーバーの仮想化によってまず削減できるのは、遊んでいるサーバーによって消費される電力。以前から使ってきた業務システムを省電力性能が高い最新サーバーに乗せ替えれば、さらに高い削減効果が得られます。
また、経営の観点からは、グリーンITに取り組むことによる企業イメージの向上も見逃せません。企業の社会的責任(CSR)への対応度が企業価値にはね返ってくる今、グリーンITへの取り組みは最重要の経営課題ともなっています。
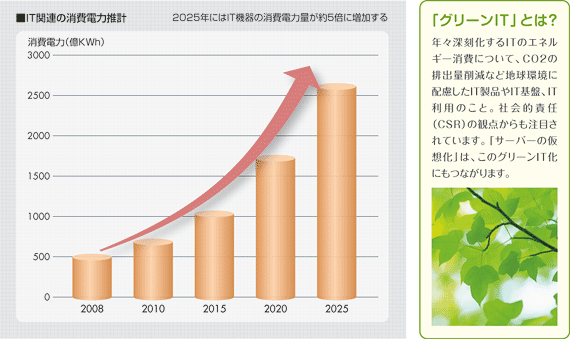
サーバーのセールスポイントに仮想化対応機能の充実度が浮上
このように、サーバーの仮想化が企業コンピューティングの世界における大きな潮流となった今、サーバー製品の側でも仮想化対応機能の充実度をセールスポイントの一つに掲げるようになってきました。
ハードウェア面でのポイントは、「サーバー仮想化にともなって必要となる処理をいかに高速化しているか」ということ。以前はサーバーメーカーが独自の回路を開発・搭載する必要がありましたが、現在ではサーバー用CPUに仮想化支援機構が標準で内蔵されているものもあります。
ソフトウェア面でも、ポイントは「仮想化にともなって必要となるソフトウェア機能をいかに充実しているか」にあります。
例えば、サーバーの動作を監視するには、サーバー本体(物理サーバー)と仮想化されたサーバー(仮想サーバー)の両方を区別して扱える能力が不可欠。トラブルが発生した時に、どの物理サーバーに含まれるどの仮想サーバーが発生箇所かを的確につかむことができなければ、適切な対策を打つことはできません。
また、サーバーの使用率を高めるために頻繁に行われるのが、不必要に割り当てた仮想サーバーによって浪費されているシステム資源(CPU、メモリー、ハードディスクなど)を、忙しい仮想サーバーに振り向ける操作。仮想サーバーへのシステム資源割り当てをいつでも自由に変更できる運用管理ツールは、ぜひ備えておきたいものです。
中堅・成長企業での採用に最適なのは設置面積最小のブレードサーバー
一方、サーバー仮想化のおもな狙いが設置面積の圧縮にある場合は、物理サーバーの大きさが最重要のチェックポイントとなります。この観点に基づいてサーバー製品を選ぶ際は、高性能タワー型サーバー、薄型ラックマウント型サーバー、ブレードサーバーの3タイプに分けて考えるとよいでしょう。なかでも、中堅・成長企業にとってお勧めなのが薄型ラックマウント型サーバー、ブレードサーバーの2タイプです。
仮想化の有無にかかわらず従来から広く使われてきたのは、薄型のラックマウント型サーバーです。このタイプのサーバーは19インチラックと呼ばれる汎用筐体のラック(棚)に差し込む構造になっていて、占有する高さによって1U(44.45mm)や2U(88.9mm)などに規格化されています。19インチラックの高さは最大で45Uありますから、理論的には1Uの高さのサーバーなら、一つの筐体(平均的なサイズは幅700mm×奥行き900mm×高さ2,200mm)の中に45台までのサーバーを詰め込めるわけです。
中堅・成長企業にもっともお勧めできるのは、最小の設置面積となるブレードサーバーです。最大の特長は、汎用筐体ではなく、各メーカーが独自に設計した筐体の中に数台から十数台のサーバーを装着できること。1サーバーあたりの高さは1U未満になりますから、わずかなスペースに大量のサーバーを統合することができるのです。また、専用コネクターを採用することによってケーブルの本数を減らしてあるなど、各メーカー独自の工夫が凝らされている点でもブレードサーバーは魅力的です。
 シャーシ+ブレードで44.45mm未満。配線も容易なブレードサーバー
では、ブレードサーバーとは、どのようなサーバーなのでしょうか。これまでのタワー型サーバーやラックマウント型サーバーとはどこが違うのでしょうか。ここでは、国内有力メーカーの製品を例に取り上げ、その特長を紹介していくことにしましょう。

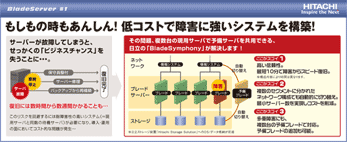
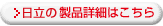
まず、外観については、シャーシと呼ばれる箱の中にブレード(刃)を挿して使う点が他のサーバーと異なります。
シャーシの寸法の規格はラックマウント型サーバーと同じ。高さは6U(日立製作所のBlade Symphony BS320の場合)から7U(富士通のPRIMERGY BX600S3シャーシの場合)程度ですから、汎用の19インチラックにラックマウント型サーバーと同居させるのも容易です。
このシャーシの前面には、垂直のスロットがいくつも並んでいます。このスロットは、サーバーの本体となる「サーバーブレード」を装着するための場所となるものです。スロットの数は製品によって異なりますが、Blade Symphony BS320とPRIMERGY BX600 S3シャーシの場合はどちらも10個。6Uまたは7Uの高さに10台のサーバーを収容できるわけですから、1台あたりの高さは0.6Uから0.7Uという計算になります。
これまでのサーバーと大きく異なるのは、電源、キーボード、マウス、ディスプレイ、ネットワーク(LAN)とのつなぎ方です。ラックマウント型サーバーではこれらのコードやケーブルを各サーバーの背面に接続する必要があり、筐体の背面がごちゃごちゃになってしまうことは避けられませんでした。一方、ブレードサーバーでは、「バックブレーン」と呼ばれるシャーシ内部にあるコネクタで接続するか、これらの機器とサーバーブレードとをケーブルを介さずに接続することができる「ミッドプレーン」というコネクタを採用。背面がスマートになるだけでなく、導入や交換時の作業量も大幅に軽減されています。
各サーバーブレードのハードウェア性能は、1Uサイズのラックマウント型サーバーとほぼ同等とみてよいでしょう。クアッドコア(4個の心臓部を1チップに収めたもの)のCPUを搭載したモデルなら、データベースなどの高負荷処理にもらくらく対応できます。

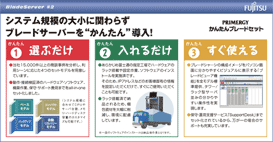

運用管理ツールとの組み合わせで業務システムを柔軟に運用できる
このブレードサーバーは、二つの方法で仮想化することができます。
一つは、各サーバーブレードに仮想化OSを組み込み、複数のOSを動作させる方法。ミニマム1台から始められるので経済的ですが、その1台にトラブルが発生すると、すべての業務システムが停止してしまうというリスクがあります。停止してもビジネスに致命的な影響が及ばないような用途、例えばファイルサーバーやプリントサーバーなら、この方法で仮想化してもよいでしょう。
もう一つは、仮想化OSを組み込んだ2台以上のサーバーブレードを用意しておき、稼働させる業務システムを必要に応じて入れ替える使い方です(メーカーによってはストレージ上のハードディスクに仮想OSを入れることで実現)。例えば、3台のサーバーブレードを導入しておいて、月中は販売管理システムに2台と経理システムに1台、経理締めの月末には経理システムに2台と販売管理システムに1台というように割り当てを柔軟に変更。仮に1台にトラブルが発生しても、販売管理システムと経理システムに1台ずつ割り当てれば最低限の業務処理機能は確保できます。停止しては困るような重要システムのサーバーは、ぜひ、こちらの方法で仮想化することをお勧めします。
●ブレードサーバー導入事例
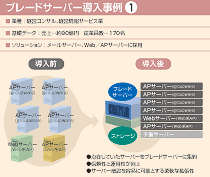
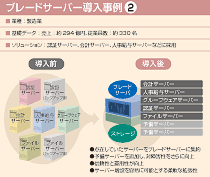
このように、サーバーの仮想化とブレードサーバーへの移行は企業に様々なメリットをもたらします。本質的なメリットである、サーバーの使用率向上や業務システムの延命などが企業に強い力を生み出すことは言うまでもありません。グリーンITへの貢献やブレードサーバーへの移行に伴う設置面積の圧縮といった二次的なメリットも、企業の成長を間違いなく後押しします。ますます厳しさの増す市況環境の中で、コスト削減と確かな競争力を確保していくためにも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
(文:山口 学)
|