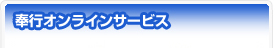���ۓI�ȉ�v��ɕ��������킹��ׂ��A���{�̉�v��ɂ����Ă��u���ۓI�����͂����߂邽�߂̊�Ə��̓K���ȊJ���v��ړI�̒��S�ɁA�l�X�Ȗ@�������s���Ă��܂����B����́u���[�X��v��v�ɏœ_�����āA�����̔w�i��K�p��̒��ӓ_���ɂ��ĉ���������܂��B
������Ƃɂ����ẮA�]���̏������F�߂��܂����A�����Ƃ̐M������R���v���C�A���X���ɂ���������Ă��邽�߁A�������\�ւ̉e���⎑�Y�Ǘ��ɂ�����Ή������O�ɍl����K�v������܂��B
�@������v�Ƃ͌Œ莑�Y�̎��v�����ቺ���A�����z�̉���������߂Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɁA���̏������Œ��뉿�z�����z�����v�����̂��Ƃ������A���{�ɂ����Ă�����17�N4��1���Ȍ�J�n���鎖�ƔN�x����K�p����Ă��܂��B
�@������v�����ɂ́A���ۓI�ȉ�v��ɏ������K�Ȋ�Ə��̊J����ړI�Ƃ���Ƃ��낪����܂��B����܂ł����ۓI�ȉ�v��ւ̑Ή��́A�L���b�V���t���[�v�Z���̊J���`�����A�Ō��ʉ�v�A���Z���i��v�A�ސE���t��v���̓����Ȃǂɂ����Ă�����Ă���A������v�̐��x�������̂ЂƂƌ����܂��B
�@�č���v���h�`�r�i���ۉ�v��j�Ȃǂ́A�����Ɠ��̕ی��ړI�Ƃ��A�����̑Ή������Ă��܂������A���{�ɂ����Ă͂��̑Ή����x��Ă���A���{��Ƃ����\�����Ə��ɂ��Ă͊C�O�����Ɠ�����̐M������������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����@��������܂����B���Ɍ�����v�ɂ����ẮA���{�ł̓o�u�����ɑ����̊�Ƃ��s���Y������A�V�K���Ƃ��s�����߂̑��z�������s�����Y�傳���܂������A���ۂ̉��l�����뉿�z��啝�ɉ����ƂȂ��Ă��܂����B
�@����̃��[�X��v��̉����́A���������u��Ə��̓K���ȊJ���v�Ƃ�������̒��ň������̃��[�X����ɂ��Ă�����㎑�Y�Ƃ��Čv�シ�邱�ƂƂ��A���K���ȏ��J�������Ă������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���ƌ�����ł��傤�B
�@�����̉�v���Ő��̉����͓��{��Ƃ̍��ۓI�M�p�͂��A�b�v���A�����͂����߂�_��������܂��B����O���[�o���X�^���_�[�h�͈�ʓI�ł���A���̂悤�ȉ����ɃX�s�[�f�B�ɑΉ����Ă����K�v������܂��B
�@
�@��Ɖ�v��ψ���́A����19�N3��30���Ɂu��Ɖ�v���13�� ���[�X����Ɋւ����v��v�y�сu��Ɖ�v��K�p�w�j��16�� ���[�X����Ɋւ����v��̓K�p�w�j�v�����\���܂����B���̉������āA����19�N�x�Ő������ɂ����āA�V�������[�X����ɌW��Ŗ���̎戵�����K�肳�ꂽ�̂ł��B
�@���ۓI�ȉ�v�̔F���ɂ����ă��[�X����Ƃ́A�t�@�C�i���X�E���[�X�i�L���s�^�����[�X�j����ƃI�y���[�e�B���O�E���[�X����ɕ��ނ���A�ׂ����@�I���߂��o�ώ��Ԃf������v�̍l�������̗p���Ă��܂��B
�@���܂ł̓��{�̉�v��ł́A���L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X��������Y�v�ス���A���Y�v��Ɠ��l�̏��𒍋L���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�������������邱�Ƃ��u��O�����v�Ƃ��ėe�F���Ă��܂����B���́u��O�����v�͓��{�Ŕ��ɑ������p����Ă��܂����A�u������v����Z���i��v�Ƃ̐��������Ƃ�Ȃ��v�u�����������d������ϓ_����̍������̓K���ȃf�B�X�N���[�W���[�i���Ƃ��A�����Ɠ���������������ɂ����j�v���̗��R�ɂ��A�u��O�����v�������I�ȏ����A�܂莑�Y�v�シ�鏈�����������邱�Ƃ����߂�ꂽ�̂ł��B
���t�@�C�i���X�E���[�X����Ƃ�
���[�X���Ԃ̒��r�ɂ����ă��[�X�_����������邱�Ƃ��@�I�i�_����s�ɂȂ��Ă���Ȃǁj�܂��͌o�ϓI�i�_���͉�ł����Ă���ɑ����̈�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃǁj�ɂł��Ȃ�����ŁA�؎肪���[�X������������炳���o�ϓI���v�������I�ɋ��邱�Ƃ��ł��A���R�X�g�������I�ɕ��S���邱�Ɓi�t���y�C�A�E�g�j�ƂȂ����������܂��B�v����Ƀ��[�X���Y���g�p���Ă��邪�A���Ђŏ��L���Ă���ꍇ�Ɠ��l�̌��ʂ���є�p���������Ă���ƌ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A�t�@�C�i���X�E���[�X����Ƃ��ĕ��ނ���܂��B
�܂��A���݉��l��A�܂��͌o�ϓI�ϗp�N����̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ��A�t�@�C�i���X�E���[�X����Ɣ��肳��܂��B
| ���݉��l� |
���s�\�̃��[�X���Ԓ��̃��[�X�����z�̌��݉��l���A���Y���[�X�����̎؎�̌��ό����w�����z�̂����ނ�90���ȏ�ł��� |
| �o�ϓI�ϗp�N��� |
���s�\�̃��[�X���Ԃ��A���Y���[�X�����̌o�ϓI�ϗp�N���̂����ނ�75���ȏ�ł��� |
���I�y���[�e�B���O�E���[�X�Ƃ�
�t�@�C�i���X�E���[�X����ȊO�̃��[�X����̂��Ƃ������A�����^������ݎ̎���͂���ɊY�����܂��B�i�}1�Q�Ɓj
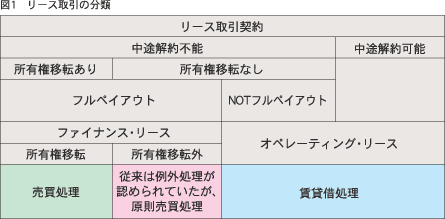
�@�]���́A�u���[�X����̕��ށv�ɂ����āA���L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X����́A��������ɏ�������v�����������Ƃ��Ȃ�����A���̒��L��v���Ƃ��āA���ݎ؏������O�I�����Ƃ��ėe�F���Ă��܂����B�������A���L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X�ł����Ă��A�o�ϓI���Ԃ����[�X�����������ꍇ�Ɠ����ł��邱�Ƃ���A����͒��ݎ؏����̗e�F��p�~���A�����������`���t���邱�ƂɂȂ�܂����B�i�}�P�s���N�F�̕����j
�@���̃��[�X��v��̓K�p�́A����20�N4��1���Ȍ�J�n����A����v�N�x����ю��ƔN�x����Ƃ���Ă���A�l�����������\�Ɋւ��ẮA����21�N4��1���Ȍ�J�n����A����v�N�x�y�ю��ƔN�x�ɌW��l�����������\����K�p���܂��B
�@�܂��A�K�p�͈̔͂́A���Z���i����@�̓K�p�����Ёi����Г��j�₻�̎q��Ћy�ъ֘A��ЁA��Ж@��̉�v�č��l��ݒu�����Ёi�����̎��{�̋��z��5���~�ȏ㖔�͕��̍��v�z��200���~�ȏ�̉�Ёj�y�т��̎q��Ђ��ΏۂɂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A�u������Ƃ̉�v�Ɋւ���w�j�v�œK�p�ΏۂƂ�����Ƃ�A�d�v���̖R�������[�X����Ń��[�X�_��1��������̑��z��300���~�ȉ��̂��́A���[�X���Ԃ�1�N�ȓ��̎�����Ɋւ��ẮA��O�I�ȏ������F�߂��Ă��܂��B
�����Y�v��
���[�X����J�n���ɁA�ʏ�̔�������ɏ�������v�����ɂ��A���[�X�����Ƃ���ɌW��������[�X���Y����у��[�X���Ƃ��Čv�サ�܂��B�v����z�ɂ��Ă͌����Ƃ��āA���[�X�_��������ɍ��ӂ��ꂽ���[�X�����z����A����Ɋ܂܂�Ă��闘�������z�̍����I�Ȍ��ϊz���T�����܂��B���̗��������z�́A���[�X���Ԃɂ킽�藘���@�ɂ��z�����܂��B
���������p
���[�X���Y�Ɋւ��ẮA���N�������p���s�����ɂȂ�܂��B
���ӓ_�Ƃ��ẮA���L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X����ɂ��ẮA���L���ړ]�t�@�C�i���X�E���[�X����̂悤�Ɏ��ȏ��L���Y�Ɠ���̕��@�ɂ��K�v�͂Ȃ��A��z�@�A�����@�A���Y�����@���̒������Ƃ̎��Ԃɉ��������̂�I��K�p������̂Ƃ���Ă���_�ł��B
| �@ |
�ϗp�N�� |
�c�����z |
���p���@ |
���L���ړ]
�t�@�C�i���X�E���[�X��� |
�o�ϓI�ϗp�N���i�o�ϓI�g�p�\�\�����ԁj |
���Ȏ��Y�Ɠ��l |
���Ȏ��Y�Ɠ��l |
���L���ړ]�O
�t�@�C�i���X�E���[�X��� |
���[�X���� |
���� �[�� |
��z�@�A�����@�A���Y�����@�Ȃǂ�I�� |
�Ȃ��A���L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X����ɂ����āA�藦�@���̗p�����Ƃ����ȏ��L�̌Œ莑�Y�̏��p���@�Ƌߎ�������@��I���������ꍇ�ɂ́A�����@�̗̍p�̑��A�c�����z��10���Ƃ��Čv�Z�����藦�@�ɂ�錸�����p����z�ɁA�ȕ֓I��9����10���悶���z���e���̌������p����z�Ƃ�����@���F�߂��Ă��܂��B
�@���[�X��v��̕ύX���A����19�N�x�Ő������ł́A����20�N4��1���Ȍ�Ɍ_�鏊�L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X����ɂ��Ă͔��������������ƂȂ�܂����B
�@���p���@�̓��[�X���Ԓ�z�@�ƂȂ�A���ؐl�����ؗ��Ƃ��Čo�������ꍇ�ɂ����Ă���������p��Ƃ��Ď�舵���܂��B�������A�Ŗ���̎؎葤�̌������p���@�̓��[�X���Ԓ�z�@�Ɍ��肳��Ă��܂����A��v��̓K�p�w�j�́A��z�@�A�����@�A���Y�����@���̒������Ƃ̎��Ԃɉ��������̂�I��K�p����Ƃ���Ă��܂��̂ŁA��v��A�Ⴆ�����@���̗p�����ꍇ�ɂ́A�Ŗ���͒�z�@�ł��̂ŁA�\���������K�v�ƂȂ�܂��B
�@����łɂ��ẮA�@�l�Ŗ@�Ɠ��l�ɁA��������ɏ����������ƂȂ�̂ŁA�؎葤�����[�X��ЂɎx�������[�X���i���������������j���ېŎd����Ƃ��ĔF�߂��A�d���T���ɂ��ă��[�X����J�n���Ɉꊇ���čs�����Ƃ��ł��܂��B
�@���p���Y�ɌW��Œ莑�Y�łɂ��ẮA��������݂��葤���[�ł��錻��̎戵�����ێ�����邱�ƂƂȂ邽�߁A�V���ɌŒ莑�Y�ł��������邱�Ƃ͂���܂���B
�@���i�K�ɂ����āA�������(����ƁA���{��5���~�ȏ㖔�͕����z200���~�ȏ�̑��ЈȊO�̉��)�ɂ��Ă͏]�����l�A���L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X����ɂ��Ē��ݎ؏����ɂ�邱�Ƃ��F�߂��Ă��܂��B�������A��L�̂悤�Ȏd���T���̈ꊇ�������A���Y�Ɍv�シ�郁���b�g������܂��̂ŁA������Ƃɂ����Ă����[�X����̌v��ɂ��Č�������K�v������܂��B
�@
�@�t�@�C�i���X�E���[�X����Ɋւ��ẮA�@�l�Ŗ@��́A��v��܂���������ɏ�������v�����������ƂȂ�܂��B�������A�؎葤�����ݎ؏������s�����ꍇ�ł����Ă��A���ؗ������z�����p��Ƃ��Ď�舵�����̂Ƃ���܂��B�Ȃ��A�Ŗ���̎؎葤�̌������p���@�̓��[�X���Ԓ�z�@�Ɍ��肳��Ă��܂����A��v��̓K�p�w�j�́A��z�@�A�����@�A���Y�����@���̒������Ƃ̎��Ԃɉ��������̂�I��K�p������̂Ƃ���Ă��܂��̂ŁA��v��A�Ⴆ�����@���̗p�����ꍇ�ɂ́A�Ŗ���͒�z�@�ł��̂ŁA�\���������K�v�ƂȂ�܂��B
�����[�X����̌���
�t�@�C�i���X�E���[�X�A���ɏ��L���ړ]�O�t�@�C�i���X�E���[�X����́A�u�ݔ��������ɑ��z�̎�����K�v�Ƃ��Ȃ��v�u�����������ȒP�v�Ȃǂ̗��R������{�����ł͑������p����Ă��܂��B
�������A����̉������Ă��̎�����s���ꍇ�A�ݎؑΏƕ\��Ƀ��[�X���Y�E���[�X�����v�コ��邽�߁A���Ȏ��{�䗦�̒ቺ�Ȃǂ��N����܂��B��ƂƂ��ẮA������p�̈����⎖�������̊ȕւ������ň��ՂɃ��[�X��I�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B�ݔ����������s���ہA�ݎؑΏƕ\�ɋy�ڂ��e���⎑���J��E���̑����X�N�����l��������ōw���ɂ���̂��A���[�X�ɂ���̂����������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
���I�y���[�V�����̐��̐���
�����Y�Ǘ�
����܂ł́A�o�^����Ă��Ȃ��������[�X������A���[�X���Y�Ƃ��Ď��Y�Ǘ�������K�v�����o�Ă��܂����B���p���@���K���������̎��Y���l�̏����ƂȂ�Ȃ��P�[�X�����邽�߁A���ӂ��K�v�ł��B�܂��A���Y�Ǘ��p�̃V�X�e�������Ă���ꍇ�A����̉����ɑΉ��ł��邩�ۂ��̊m�F�����O�ɍs���Ă����K�v������܂��B
���o������
���[�X�̎x�����͂���܂ő��̔�p���l�̏������s�������߁A�����ɓ��ʂȏ�����K�v�Ƃ��Ă��܂���ł������A�_�̗��������z�̎Z�o�⌈�Z���̌������p���Ŗ��Ɋ֘A���鏈���������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�@����玑�Y�Ǘ���Ŗ��������s�����߂̑̐����K�v�ƂȂ�A�V�X�e���̑Ή����K�v�ƂȂ�܂��B�����ɑ�������v�V�X�e���E�Œ莑�Y�Ǘ��V�X�e�����K�v�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���O�ɏ��������Ă������Ƃ��厖�ł��B����������Ŗ��ɂ��A�����鏈���Ȃ̂ŁA�֘A����V�X�e���Ƃ̘A����������ɓ��ꂽ�̐��̐������K�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�܂��A��O�ɏ�����Ă������[�X���Y����э����������\�Ɍv�コ��邱�ƂŁA�Ɩ��ւ̕��S�͑����X���ɂ���܂��B���G�������v�ƐŖ��ł����A�ώG�ɂȂ邱�Ƃ͊�ƌo�c�ɂƂ��Ĕ����������̂ł��B��Ƃ̎��Y�Ǘ��̋Ɩ����s�ɂ��ЁA�Œ莑�Y�E���[�X���Y�Ǘ����X�s�[�f�B�Ɋm���ɐ��s�����z�@�Ή��́u���p��s21Ver.�W�iSuper�V�X�e���ȏ�őΉ��j�v�����𗧂Ă��������B
�@