■ネットビジネスにおける決済(代金回収)の重要性
―「奉行シリーズ」をご利用の企業のなかにも、ネットビジネスに興味を持たれている企業も少なくないと思います。企業経営の視点で考えてみますと、とくに、見込める売上やキャッシュフローは重要な点です。その中でも決済、代金回収についてはしっかりとした仕組みにしておく必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
和田 決済の問題は企業にとって非常に大切なことです。それはネットビジネスにおいても同様です。ただし、ネットの世界における決済は、多岐にわたっていますよね。まずは、三菱東京UFJ銀行の天野部長に、銀行の視点から、決済についてお話をお伺いします。天野部長、現在のネット環境における決済全般について、ご説明いただけますか。
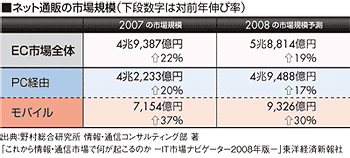 天野
天野 ネットビジネスの黎明期には、郵便局や銀行での振り込み、あるいは代金引換え、クレジットカードによる支払いといった代金回収方法が主流でした。その後、コンビニエンスストアでの支払いなどに加えて、最近ではネットバンキングによる連動決済や銀行ATMでの支払いなど、新しい決済サービスが続々と登場しました。現在では、決済方法は随分と多岐にわたっています。
和田 ディー・エヌ・エーさんは、ネットオークションやモバイルコマースなどの事業を通して、決済サービスの重要性を肌で感じてらっしゃるのではないでしょうか。
南場 そうですね――。ネットビジネスにおける決済・代金回収の重要性は非常に高まっています。私たちはネット上で売り手と買い手を結びつけることを生業としてきました。もちろんそこでは売るだけでなく、代金を回収することも重要になります。しかし、多岐にわ
たる決済方法のそれぞれを店舗の運営者が一つずつ取り入れるのは、たいへんな手間が掛かることです。そこで、当社は三菱東京UFJ銀行さんと共同で、ネットビジネス向け決済代行サービスの株式会社ペイジェントを設立しました。
和田 決済代行サービスの会社を設立された背景には、決済サービスの重要性と、その一方の煩雑さなどがあるのですね。となると、ペイジェントは時代のニーズにマッチしていますね。具体的に、ペイジェントの特長はどんな点にありますか。
天野 ペイジェントは、「安心、便利な決済手段をワンストップで、安価に提供する」ことを旨としています。一度の契約で、クレジットカードやコンビニエンスストア、多数の銀行、ゆうちょでの代金決済が可能になります。2006年の5月に設立し、約2年半が経過しました。
南場 もともと私たちには、eコマースのノウハウを店舗や事業者さんにトータル・ソリューションという形で提供したいという思いがありました。店舗規模にかかわらず、決済に関わるフルソリューションをワンセットで提供できるペイジェントは、なくてはならない機能であるとともに、まさにネットビジネスにおける私たちのノウハウの結集ともいえます。
―決済サービスに着目されたきっかけは何だったのでしょうか。
天野 事業の構想段階で、我々はB2B2C、B2Cのビジネスを展開しているECサイトにご協力をいただき、ヒアリングなどを実施しました。そこから、決済手段をまとめて提供してほしいというECサイトのニーズを掴みました。また、決済サービスを利用する際には、ECサイトがシステム対応しなければならないこと
も分かりました。このシステム対応を極力簡単にしたい、といった声もありましたので、これらのニーズに対応する形でペイジェントが生まれました。
南場 お金を扱うには何よりも信頼が重要です。そういう意味で、信頼の厚い三菱東京UFJ銀行さんとの合弁は有意義だったと思っています。現在では経営的にも安定し、お客様からの信頼も高まりました。
和田 お客様から信頼を得るには、お客様の声を聞き、生かしていくことが非常に大切ですね。実際、ペイジェントのサービスをご利用になられたお客様の反応はどうでしたか。
 天野
天野 eコマースを展開されている事業者のお客様方からいただいた声には大きく二つあります。一つには、売上が伸びたという声が届いています。買い手からみて、様々な方法の決済が利用できることはたいへん便利で、好評のようです。なかには、売上が1.5倍以上に増えたという会社もありました。
もう一つは「売上の消し込み」機能についての反応も多くいただいています。売上の消し込みはリアルの店舗でも同じですが、事務が非常に煩雑です。人手が掛かり、コストもかかります。ペイジェントのサービスでは、買い手が代金の支払いを完了したとき、売上管理番号ごとに消し込みを行い、そのデータをリアルタイムで提供します。このため、eコマース事業者の売上管理システムにおいて、自動的に消し込むことができます。この売上消し込みの自動化、システム化機能は、OBCさんの「商奉行」とデータの連携がとれ、作業の効率向上の面でも優れています。
和田 まさに、仰る通りです。ネットバンキング・サービスと「商奉行」、そしてペイジェントを結びつければ、経理事務などの作業効率の向上になり、大幅なコストダウンが図れます。また、こうした経理事務についてですが、ネットバンキング・システムにおいて、当社は「奉行シリーズ」との連携で、三菱東京UFJ銀行さんと長年お付き合いをさせていただいていますね。
天野 そうですね、十数年以上の長いお付き合いになります。当行の「せるふバンク」「U-LINE Xtra(ユーラインエクストラ)」というネットバンキング・サービスは、OBC「奉行シリーズ」と連動しています。このサービスを利用すると、業務担当者はオフィスにいながら、振込・振替、総合振込、給与振込といった処理依頼をご自身でできます。
―なるほど。「奉行シリーズ」は三菱東京UFJ銀行さんのネットバンキングと連携することで、いっそうの業務効率化に役立てていただいているのですね。
話はECサイトに戻りますが――、決済方法を充実させることは、それだけ買い手の選択肢が増え、より買い物がしやすくなるということですよね。実際に、ディー・エヌ・エーさんはペイジェントのユーザーでもいらっしゃると聞いていますが。
南場 当社はペイジェントの共同設立企業である一方で、ペイジェントの第一号ユーザーでもあります。現在、「ビッダーズ」という当社運営のショッピングモールでは、ほとんどの店舗さんにペイジェントの決済代行サービスをご利用いただいています。また、「モバオク」といったケータイオークションサイトではペイジェントを利用して、「エスクロー決済」をオークションの買い手・売り手に提供しています。ともに、サービスのレベルとしてはすばらしいものができました。ペイジェントという事業の成功だけでなく、eコマースに付随するサービスについてユーザーの満足度アップに大きく貢献できたという点でも、いい取り組みだと思っています。
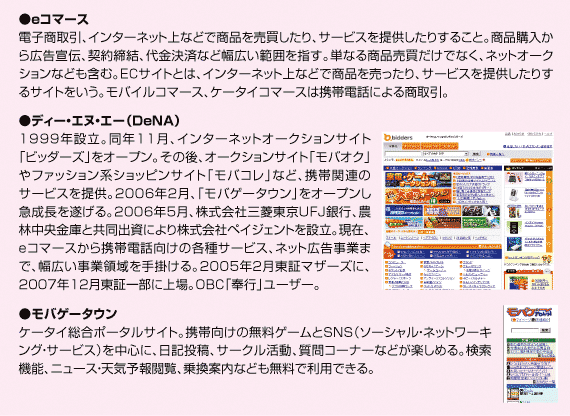
■少ない資本でも知恵と地道な努力で差のつくネット店舗運営
―ネットビジネスにおける決済サービスの重要性から、ネットバンキングによる業務効率向上までお話をいただきました。ネットビジネスは、様々な点で魅力があるといわれていますが、いかがでしょうか。また、今後どうなっていくとお考えでしょうか。
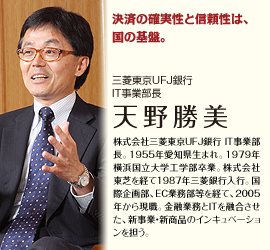 天野
天野 ネットでの物販の市場規模、これは侮れないものになっています。ペイジェントの構想段階で我々が行った調査では、百貨店が8〜9兆円、コンビニエンスストアが7兆円の年間市場規模でした。対するネットは5兆円に迫る規模になっており、なかでも、とくに我々が注目したのは伸び率です。当時、年率3割の伸びを見せていましたので、このような状況下、我々銀行としても、ネットビジネスに伴う決済サービスをどう提供していくべきか、深く考えました。
和田 南場社長から見たeコマースの魅力はどういった点にありますか。
南場 eコマースの魅力は、資金の多寡にかかわらず、平等にチャンスが与えられる点です。例えば、リアルの店舗は地の利を得るのに、相当な資本が必要です。eコマースなら、それほど資本がなくても出店でき、知恵と地道な努力で差のつく店舗運営ができます。当社のオークション&ショッピングサイト「ビッダーズ」では、出店するのに月々数万円で済みます。24時間、店を開けておけますから、寝ている間に稼いでもらえるところも魅力です。
和田 「奉行シリーズ」をご利用の企業のなかにはネット上に出店したい、eコマースを始めたいとお考えの方もいらっしゃると思います。参考になるお店はありますか。
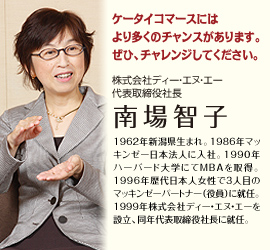 南場
南場 リアルの店舗では、3坪という狭いところで細々と梅干を販売していた人がいます。あるとき、ネット上に店舗を構え、瞬く間に全国区になった事例があります。その梅干屋さんは商品にものすごく自信がありました。そこで、真心込めた自社商品について、つくった本人の熱意や思いの丈をネット上に公開しました。ネットの世界では、つくり手とお客様、さらにはお客様同士のコミュニケーションができます。その梅干の美味しさは口コミで広がり、瞬く間にたくさん売れるようになりました。規模は小さくてもアイデアと努力次第で全国区になれます。ネットで成功して、リアル店舗の門構えが大きくなったという話を聞くと、本当にうれしいです。
より具体的にいいますと、店舗を全国区にするには、まず、店舗を目立たせるにはどうしたらよいのか? といったことを考えるとよいでしょう。それから、リピータを増やす、検索結果での上位表示など、ネットの世界には成功するためにすべきことがいくつかあります。それらを一つずつ積み重ねることが大切です。「ビッダーズ」では評判の店舗を表彰していますが、対象となる店舗は地道なことをしっかりとなさっています。
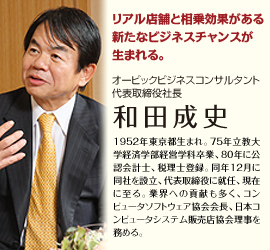 和田
和田 リアル店舗と同じように、基本的なことをしっかりと実行することが大切である一方で、ネットの世界では考え方、やり方一つで、リアル店舗と相乗効果がある新たなビジネスチャンスが生まれるわけですね。
―では、その魅力あるeコマースの中でも、とくに注目されている分野はありますか。
南場 eコマースのなかでも、一番成長しているのがケータイコマースです。まだeコマースに参入していないなら、パソコンではなくケータイコマースに進出されるのが面白いのではないでしょうか。なぜなら、パソコンのほうは歴史が10年以上もあり、市場は成熟している感があります。ノウハウを蓄積しているお店も少なくないですし、競争は激化しています。それに対して、ケータイコマースが本格的に伸びたのは去年です。しかも、実質の伸び率はおそらくパソコンの2倍以上あるのではないでしょうか。
―ケータイでものが売れるのかどうか、疑問を持たれる方もいらっしゃるように思いますが、ケータイコマースでは実際にどのようなものが売れていますか。
南場 これまで、大きいもの、高いもの、食べるものはケータイでは売れないといわれていました。ところが、去年の年末はカニがたくさん売れました。最近では、ソファなどの家具や四十数万円の液晶テレビなど、高価なものが売れ筋に上っています。とくに、市場の伸びと競争という点で見ると、ケータイコマースにはより多くのチャンスがあります。ぜひ、チャレンジしてください。
■開店したその日から世界を相手にビジネスができる
―ネットビジネスの成長性やケータイコマースの魅力についてお話をいただきましたが、ネットビジネスの今後の動向について、どのようにお考えですか。構想なども含めてお話いただけますか。
南場 アメリカでは、ネットビジネスの分野でもグローバリゼーションが進み、国内外で成功している例も見られます。その点、日本におけるネットビジネスはとてもドメスティック※1です。日本のマーケットは一定の規模があり、成長が期待できるので、現状に甘んじているのかもしれません。しかし、今後は、そうはいかなくなるでしょう。海外での事業展開、販売を本格的に考えなくてはいけなくなると思っています。
今後は広義のクロスボーダー※2が本格的に立ちあがるでしょう。それに資するネットインフラ、サービスは未整備です。この部分についてのポテンシャルが大きいと思います。
天野 最初に申し上げたとおり、ペイジェントのコア・コンピタンスは、「安心、便利な決済手段をワンストップで安価に提供する」ことだと考えています。今後は、より成長が見込まれるケータイコマース向けの決済サービスを充実させていく考えです。具体的には、KDDI様と弊行が共同で設立したケータイ銀行「じぶん銀行」を使った決済サービスを7月から開始しています。また、新たな決済方法として、携帯電話料金により代金を回収する「携帯キャリア決済」も提供を開始します。
海外進出やクロスボーダーにおいて欠かせない外国為替に関するところは、銀行がノウハウを持っている部分でもあります。海外への事業展開でいえば、中国のマーケットは、日本製品の品質の良さなど、いろいろな点で日本に興味を持っています。中国をはじめとする外国の方が日本の店舗で買い物をすることも増えるでしょう。そのときの決済手段なども、ペイジェントのサービスに加えていければと思っています。
和田 それはすばらしいですね。事実、市場の変化は目まぐるしく、ネットビジネスの急速な発展にともない、お客様にご提供するサービスや企業を支える基幹業務システム、企業のキャッシュフローを健全化する決済サービスなどの各システムが融合した時代が始まっています。「奉行シリーズ」も、社会情勢の変化を捉え、常に最新のテクノロジーに対応すべくバージョンアップして参りました。
南場 ペイジェントの事業はまだまだ可能性があり、とても楽しみです。現在のペイジェントの決済サービスは非常に高いレベルになっていて満足していますが、ここに留まらずに、さらに新しい決済手段への対応を続けていくことが大切だと思っています。
 和田
和田 決済の確実性と信頼性は、ビジネスの発展にとって、たいへん重要な要素ですからね。
天野 物の流れは目に見えて注目されやすいのですが、決済の流れは後々になりがちです。しかし、ビジネスはただ売るだけではなく、決済されて初めて成立します。ですから、この決済の確実性と信頼性は、国の基盤だといってもいいでしょう。今回のペイジェントの共同事業は、すでにネット事業として成功しているといえます。さらにケータイ社会のなかで、大きく展開していき、社会に繋がっていくことが重要だと考えています。
和田 ペイジェント、三菱東京UFJ銀行、ディー・エヌ・エー、OBCの4社のシステム連携が、「奉行シリーズ」をご利用の皆様の新たなビジネスチャンスを創造し、新たなフィールドでの成長をご支援します。ぜひその新たな可能性にチャレンジしていただきたいですね。
今後ますます4社が協力し、成長企業に求められるサービスをご提供して参ります。本日はありがとうございました。
※1 domestic:国内の、国内的な、国産の。ビジネス用語として、インターナショナル、グローバルの対義語として用いられる。ドメスティックな企業、ドメスティックな価値観など。一般的には、家庭(内)の、家庭的な、自家製の、といった意味もあり。
※2 cross-border:国境を越えた、国家間を跨った。またはそれを行う人やビジネスの形態。クロスボーダー取引、クロスボーダーM&Aなど。