|
生産性を高めることによって、企業の収益力を強化する―――。この古くて新しい経営課題をクリアするには、ITをフル活用することが欠かせません。どのような企業にも求められているのは、情報共有や各種手続きの効率化や営業部門の生産性アップなどの業務効率改善。これを解決するためのアプリケーションとしては、ワークフロー機能を備えたグループウェアや営業支援システム(SFA)が代表的です。さらに、これらのアプリケーションを“いつでもどこからでも”利用できるようにするために、導入すると便利なのが超小型パソコンやPDA、携帯電話・PHS、そしてこの両者を兼ね備えたスマートフォンです。これらのモバイル端末を使った生産性向上策や、なかでも威力を発揮する最新型のモバイル端末、スマートフォンを紹介します。
業務効率と生産性を高め、企業を強くする最新のITツール
企業内を横断した情報統制が業務効率・生産性向上を実現する
売上を伸ばしながらもコストを抑え、将来に向けての投資やイノベーションにも継続して取り組む―――。そうした「強い企業」となるには、企業活動のあらゆる領域で業務効率と生産性を高めていくことが欠かせません。生産性についてはいろいろな捉え方がありますが、ベースとなるのは「時間あたりのアウトプット」。業務効率を高めるということは、無駄な空き時間や待ち時間をなくし、時間とコストを削減することにほかなりません。
業務効率や生産性の向上は、企業にとっての「売上の向上」、「顧客満足度の向上」につながるだけでなく、「社内コミュニケーションの活性化」など、多くの効果をもたらします。そして、業務効率や生産性の向上のために重要な鍵となるのはITによる支援です。企業の社内インフラ整備や営業支援を行うべく、さまざまな業種・業務に合わせた数多くの情報機器やアプリケーションソフトが販売されています。より高い投資効率を得るためには、それら多くのツールの中から自社に合ったものを探し出すことが重要です。また、システムを導入するだけでなく、導入後の運用いかんで効果を最大限に発揮できるかどうかが決まります。システムの導入によって管理できるようになった情報を統制することで、有益な情報の活用が可能になり、情報の漏洩防止や内部統制といった企業に求められる責任感や、顧客からの信頼を喚起することができます。そのためにも、部門・部署から企業全体へと、横断的な取り組みが求められます。
ソフトとハードの相乗効果によるIT支援
パソコンとインターネットが広く普及し、さまざまなビジネス・アプリケーションが容易に入手できるようになった現在、ITの活用はビジネスに欠くことができません。
ソフトの観点から見ると、情報共有や各種手続きの効率化、営業部門の生産性向上を図るには、グループウェアや営業支援システム(SFA)の導入が効果的です。同時に、社外からこれらのシステムを活用するにはモバイル端末を準備することが欠かせません。
一方、ハード面では、「スマートフォン」と呼ばれる最新型のモバイル端末を、社外用のITツールとして選ぶ企業も増えてきました。スマートフォンはPDA(携帯情報端末)や超小型パソコンと携帯電話・PHSの特長を併せ持っており、社内ネットワーク(LAN)が引かれていない場所(例えば外出先や自宅)からでも自社のサーバーにアクセスできます。処理能力についても、ノート型パソコンに比べれば多少劣るものの、一般的な業務や事務手続きには十分なレベルが確保されています(図1)。
さらに、グループウェアや営業支援システム(SFA)も高度化が進み、対象となる業務や管理できる情報も多様化してきています。
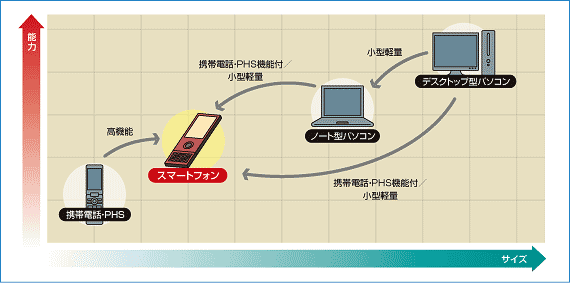
図1 ノート型パソコンより小型軽量、携帯電話・PHSより高機能なスマートフォン。いつでもどこでも企業のITを活用できる。
共同作業の時間と場所を問わないのがグループウェア
“待たない/待たせない”で各種手続きがスムーズに進む
スマートフォン対応のビジネス・アプリケーションの代表格となるグループウェアは、グループで行う作業の効率化を目的に作られたソフトウェアです。ほとんどのグループウェア製品はメール、電子掲示板(電子会議)、スケジュール表、アドレス帳、To Doリスト、ワークフロー、ファイル共有などの多様な機能を備えたスイート構成(*1)です。例えば、株式会社ネオジャパンが提供する統合グループウェア「desknet’s(デスクネッツ)」の場合、23種類のグループウェア・アプリケーションの連携が取れています。社内のLAN接続からだけでなく、社外からもWebブラウザーを介してアクセスできるのが通常です。
グループウェア最大の特長は、共同作業に必要な情報に“いつでもどこからでも”アクセスできる点です。タスク(実施すべき作業項目)とスケジュール、案件の進行状況、商品在庫などの情報はサーバーに存在しており、グループのメンバーは社内のデスクトップ型パソコンからも、外出先のノート型パソコンやスマートフォンからも操作が可能です。頻繁に外出したり出張したりするメンバーがいても、共同作業を円滑に進めることができます。
また、伝票や各種届け出が電子化されている(またはその予定がある)企業では、ワークフローの機能を利用することによって、その手続きをモバイル端末で行えるようになります。起票者にとってはわざわざオフィスに戻らなくても済むこと、承認権限者にとっては手が空いた時にどこからでも承認や決裁ができることが大きなメリットです。
一方、営業やルート販売などの部署には、営業支援システム(SFA)の導入が効果的です。管理職を含めた全員が外出していることもしばしばですから、モバイル端末と組み合わせて導入することで業務効率の向上を期待できます。オフィスに戻らなくても業務報告や事務作業を済ますことができれば、それだけ多くの時間をコア業務である商談そのものに振り向けることができるからです。
なかでも特に威力を発揮するのが、「顧客情報管理」や「商談管理」「営業プロセス管理」など、情報やノウハウの共有だけでなく、営業プロセスのマネジメントも可能にするものです。営業同士の情報共有が可能になれば、担当している営業がいなくてもお客様からの問合わせに迅速な対応ができ、それが顧客満足につながります。また、営業同士の情報共有は社内のコミュニケーションも活性化し、営業責任者の意思決定も早くなるのです。
ただし、営業支援システム(SFA)は導入後の運用いかんで成果の現れ方が異なります。
(*1)複数のソフトウェアをひとまとめにして連携が取れるようにした構成
営業支援システム(SFA)の成果を出すためには
営業支援システム(SFA)の導入で成果が得られるかどうかは利用する営業個人の意識がカギになります。「顧客情報管理」システムなどは、そのシステムを理解すれば運用効果は出ますが、営業支援システム(SFA)はシステムを導入すればそれだけで営業力の強化ができるというわけではありません。組織の営業力強化に結び付けるためには、情報発信者と受信者との間に活発なコミュニケーションが必要です。役に立つ情報を発信しても誰も反応しない、日報を書いても上司のコメントが返ってこないといったことでは、所期の目的を達することはできません。
このような課題に対して、株式会社NIコンサルティングでは、システムと運用の両面で企業の営業力強化と売上向上を支援しています。システムの提供に止まらず、その運用が軌道に乗るまでサポートしているため、人材教育に時間が取れない企業には強い味方です。
※全国規模でセミナーも開催中。
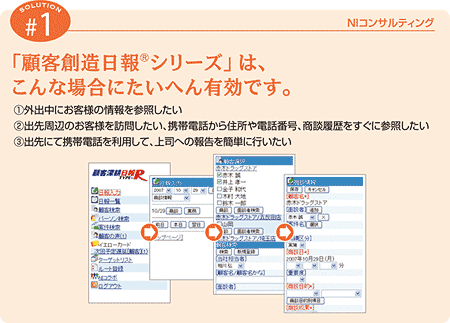
グループウェアの活用で仕事は持ち帰らない、持ち帰らせない
現在、モバイル端末を携帯する営業マンが増えていますが、スマートフォンを利用してグループウェアをどのように活用しているのでしょうか? O社の営業マン、Sさんの1日を追うことで見てみましょう。
* Sさんが朝一に出社するのは週初めだけ。たいていは取引先に直行します。取引先に向かう電車の中でまずすることは、今日一日のスケジュールの確認。営業マン各自が持つスマートフォン上のスケジュールと、サーバー上にあるメンバー全員のスケジュール表が連動しているので、自分のスケジュールだけでなく上司のスケジュールも確認できます。スケジュールの確認が終わると、急ぎの用件が入っていないか、メールもチェックします。
次に、これから会う取引先との商談を振り返っておきます。取引先ごとに情報管理がされているので、前回の商談状況や次にすべきこと、その後の上司からの指示などが一目瞭然です。その後、取引先に到着したところで出退勤届けに時刻を入力します。
Sさんには、商談中や移動中でもお客様や取引先から電話やメールがきます。例えば、「昨日出してもらった見積書ですが、本数を変更したいので出し直してもらえませんか? 急ぎでお願いしたいんですけど……」といった依頼です。そんな時は、移動中にオフィスのサーバーにアクセスし、スマートフォン上から昨日提出した見積りをダウンロードします。その場で本数と金額、日付などを変更した上で、お客様にメールで送信します。大切なお客様の要望に迅速に対応でき、次の商談先にも遅れずに到着できます。
商談が終われば、次の取引先に移動するまでのあいだに、終わったばかりの商談の内容や上司への相談事、次の訪問日などを営業日報に書き込んでおきます。こうすることで、スケジュールと商談が管理でき、他のメンバーとグループウェア上でノウハウの共有もできるようになります。
1日の商談が終わると、帰りの電車の中で、交通費や備品購入などの精算手続きを済ませてしまいます。また、決裁が必要なことがあれば、移動中に申請します。さらに、取引先で掴んだ情報や誰かに教えて欲しいことなどは、営業部門で運営している情報共有サイトに書き込みます。ときには、顔を合わせたこともない地方の営業マンから耳寄りな情報が寄せられることもあり、その場で全国の最新情報を得ることができるのです。
最寄り駅に着く頃にはすべての報告と申請が終わっており、最後に退社時刻を入力すれば、今日の仕事はすべて終了です。
*
いかがですか? スマートフォンなどのモバイル端末とグループウェアを組み合わせて活用することで、大切なお客様や取引先の要望に迅速に対応できるだけでなく、一日の大切な時間を有効に活用することができるのです。営業マン一人一人の行動が、企業に対する信頼性と顧客満足度を向上させることは言うまでもありません。(図2)
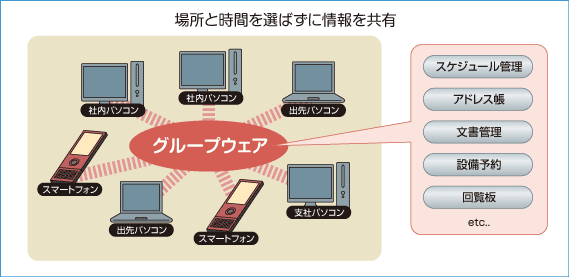
図2 グループウエアイメージ図
グループウェアの導入もパッケージからネットワークへ進化?
グループウェアは当初、情報共有ツールとしての性格が強いものでしたが、最近では、アプリケーションの強化、拡張により、さまざまなプロセスを管理できるようになるなど、内部統制も視野に入れたものに発展しています。さらに注目すべきは、機能面だけでなく利用形態の面でも進化が始まっていることです。

株式会社ネオジャパンでは、1999年よりWebベースのグループウェア・パッケージ「desknet’s」を販売し、すでに210万ユーザーを獲得していますが、昨年よりSaaS対応のオンデマンド・アプリケーション・サービス「Applitus(アプリタス)」を通じて、「desknet’s」をはじめとするさまざまなアプリケーションの提供をはじめています。
グループウェアを利用するには、通常、パッケージソフトを自社のネットワーク内のサーバー(パソコン)にインストールし、その社内ネットワークに外部からアクセスできることが必要でしたが、この「Applitus」はシステムを社内構築することなく、グループウェアをはじめとするさまざまなアプリケーションを必要に応じて選定し、ネットワーク上で利用する形態です。
したがって社内LANは不要、セキュリティの心配もなく、必要なアプリケーションをすぐに月額制で使い始められ、システム運用からも解放されるという点が優れています。
先に述べた営業支援システム(SFA)を含め、ワークフローが企業内の情報共有を一層効率的にし、社員一人ひとりの意識、行動に変化が現れます。この変化が業務効率の向上と無駄なコストの削減につながり、結果として、企業に業績の向上をもたらします。また、情報が一元管理されるようになるため、企業の信頼を失いかねない情報漏洩の防止や内部統制にも効果を発揮します。
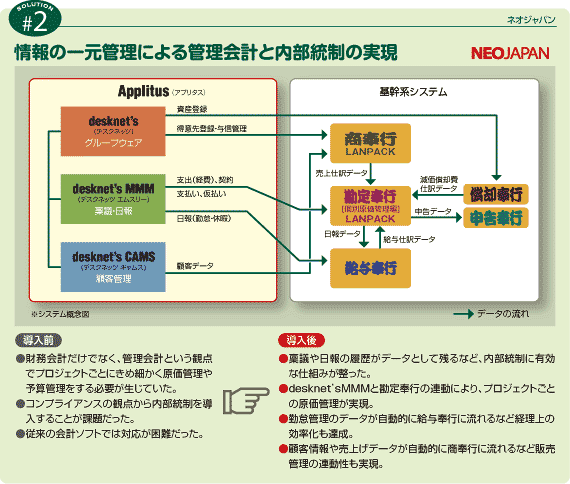
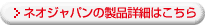
小型最強のモバイル端末、スマートフォンの最新事情
ノート型パソコンより小型軽量、携帯電話・PHSも兼ねる
ワークフローや営業の実務を支援するビジネス・アプリケーションを企業のサーバーで稼働させ、いつでもどこからでもアクセスできる仕組みを準備しておくことによって、業務の効率をさらに高めていくことができます。そのために必要となる新しいITツールが、超小型パソコンまたはPDAと携帯電話・PHSを組み合わせたスマートフォンです。
冒頭でも触れたように、業務システムに社外からアクセスするためのツールとしてはノート型パソコンも候補の一つとなります。内蔵のバッテリーで数時間は稼働させることができますし、公衆無線LANを使える場所ならオフィスと同レベルの快適なレスポンスタイムが得られることでしょう。モデム機能を搭載した携帯電話・PHSなどを併用すれば、無線LANの電波が届いていないところからも業務システムへのアクセスは可能です。
しかし、小ささと軽さ、起動時間がかからず電車待ちのちょっとした時間にもメールの確認が行えるなど、モバイル環境の利便性においてスマートフォンは、ノート型パソコンよりはるかに優れています。機種にもよりますが、典型的なサイズは縦横12cm×6cmで150g程度。上着のポケットにも無理なく収まる大きさですから、持ち歩くのも苦になりません。通話にも使えるので携帯電話・PHSを別に持つ必要もなく、携帯電話・PHSからの機種変更で乗り換えられることも魅力です。
経営的な観点からは、その対コスト性能が高く評価できます。本体価格はノート型PCの数分の一に留まりますし、追加で購入しなければならないデスクトップアプリケーションもありません。契約先も携帯電話・PHSを扱う通信会社に一本化できますから、事務手続きも簡単になります。
国内では携帯電話・PHSベースのスマートフォンが主流
現在、日本で入手できるスマートフォンには3つのタイプがあります(図3)。
●携帯電話・PHSをベースとしたもの
●PDAをベースとしたもの
●ページャー(ポケットベル)をベースとしたもの

図3 現在入手可能なスマートフォンの3タイプ
このうち、機種・台数とも国内で圧倒的なシェアを持つのは携帯電話・PHSをベースとしたものです。本体のデザイン、画面サイズ、ボタン配列などは携帯電話・PHSを踏襲していますから、パソコンになじみがない人でも気軽に使うことができ、通話の際も普通の携帯電話・PHSと同じ感覚で耳に当てて話せます。
また、長文の入力をスピーディーに行えるようにするためのアルファベットキーを備えた機種もあります。たいていはスライド式になっていますから、携帯電話・PHSとして使う時は収納したままにしておき、メールを書いたり売上日報を作成したりする時だけ本体の底面から引き出して使います。キー配列はパソコンと同じQWERTY方式になっており、両手の指を使ったタッチタイピングでの入力も可能です。
一方、PDAやページャーをベースとしたスマートフォンは、欧米で評価が高い機種を日本語化したものがほとんどです。携帯電話・PHSベースのものより本体はやや横長になってしまいますが、その分、文字を入力することが多いケースには向きそうです。
Windows(R)アプリケーションを標準で搭載した機種も
スマートフォンはグループウェアや営業支援システム(SFA)と連携させることによって真価を発揮するモバイル端末ですが、Windows Mobileが搭載されている機種なら、Webブラウザ経由だけでなく、WordやExcelなどのメールに添付されたビジネス文書も自在に扱うことができます。

例えば、富士通株式会社が今年の3月に発売した「F1100」ならば、日常的に利用する携帯電話に欠かせない「携帯性」と「使いやすさ」に加え、ビジネス文書の取り扱いができるだけでなく、指紋センサー、遠隔データ消去などのビジネスユースで求められる高いセキュリティも兼ね備え、ワンランク上のグループウェア端末として使用できます。また、戸外でのFOMA携帯としてだけでなく、社内では無線LANを利用したIP内線電話として使用できることも魅力の一つです。
このように「F1100」は、携帯電話(FOMA)、IP内線電話、Windowsパソコン、グループウェア活用のためのビジネス用モバイル端末としての機能を兼ね備え、業務用ノートパソコンと業務用携帯電話の統合を可能にする最先端モバイルなのです。
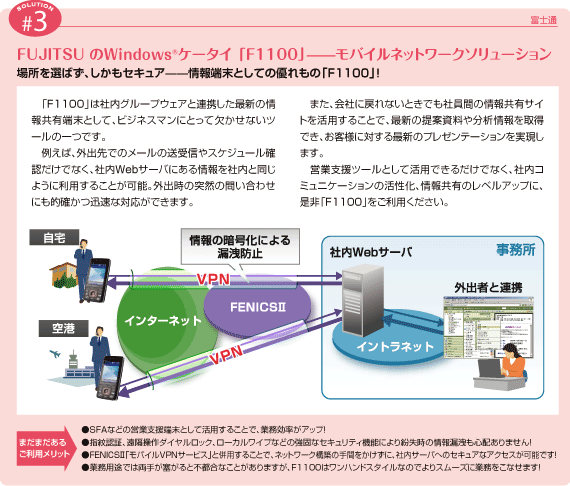
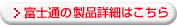
ITは、企業の業務効率を高めるためにも大きな役割を果たします。社内の連絡や各種手続きの効率化に役立つのはグループウェアとそのワークフロー機能。営業部門の生産性アップにはSFAが威力を発揮します。そのためのモバイル端末として最適なのが、ノート型パソコンより小型軽量で携帯電話・PHSとしても使えるスマートフォンです。ITツールの連動によって、個々の改善から会社全体の効率化実現へ飛躍するため、高い投資効率が期待できます。収益向上、顧客満足度向上、内部統制と、企業に求められる使命に是非、ITツールをご活用ください。(文:山口 学)
|