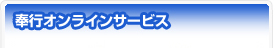2001�N�ɔ��\���ꂽ�ue-Japan�헪�v�i2003�N7�����ue-Japan�헪�U�v�j�́A���E�ō������̃u���[�h�o���h�̕��y����d�q������Ȃǂ̃l�b�g�r�W�l�X�̕��y�Ȃǂ̐��ʂ������炵�A�d�q�\���ȂǁA�d�q���{�ւ̎��g�݂������ɐi�݂܂����B���N����́uIT�V���v�헪�v�Ƃ��āAIT�ɂ��\�����v�͂̂���Ȃ�Nj����ڎw����Ă��܂��B�d�q�����@�̎{�s��d�q�\���̐��i�͊�Ɠ���IT���p�ɂ����Ă��[���ւ�肪����܂����A�S���̎����̂ɂ����Ă���i�I�Ȏ��g�݂������������܂��B
 �@���ꂩ��̓��{���l����Ƃ��A���̍ł��傫�ȎЉ�ω��́A�{�i�I�Ȑl�������ƍ���ɂ���ƌ����܂��B��ʐ��Y�Ƒ�ʏ���ɂ���Ĕɉh�����������Ă���20���I�^�̍H�ƎЉ�͏��X�ɕω����A���������O���[�o��������o�ς̂�������ϗe�𔗂��Ă��܂��B����͊����̎Љ��Ղɑ���ω��̗v�����܂��B
�@���ꂩ��̓��{���l����Ƃ��A���̍ł��傫�ȎЉ�ω��́A�{�i�I�Ȑl�������ƍ���ɂ���ƌ����܂��B��ʐ��Y�Ƒ�ʏ���ɂ���Ĕɉh�����������Ă���20���I�^�̍H�ƎЉ�͏��X�ɕω����A���������O���[�o��������o�ς̂�������ϗe�𔗂��Ă��܂��B����͊����̎Љ��Ղɑ���ω��̗v�����܂��B
���������F���Ɋ�Â��A���{���{�͎Љ�̑�ϊv�Ɍ�����IT��Ղ̐����Ɏ��g�ނ��߁A2001�N�A�uIT��{�@�v�̐����ue-Japan�헪�v�̍�����s���AIT�헪�{���i���t�{�j�哱�̂��ƁA�u5�N�ȓ��ɐ��E�Ő�[��IT���ƂɂȂ�v���Ƃ�ڕW�ɁAIT�v���ւ̖{�i�I�Ȏ��g�݂��J�n���܂����B
�ue-Japan�헪�v��5�N�ԂŁA�u���[�h�o���h�C���t���̐����Ɨ��p�̍L����A���@�\�g�ѓd�b�̕��y�A�d�q������̊������Ƃ��̊g��ɂ����āA���E�Ő�[���������܂����B������{�́A�C���t�������ɂ����Ă��A���p���闧��ɂ����Ă��A���E�ō������ƂȂ�A�Ő�[�̃}�[�P�b�g�ƋZ�p����L����IT��i���ƂƂȂ�܂����B
���̈���ł́A�ˑR�Ƃ��ĉۑ�����݂��Ă��܂��B��̓I�ɂ́A�s���T�[�r�X��A��ÁA���番��ł�IT���p�E���p�ɂ����鍑�������x�̌���A�n��␢��Ԃ̏�p�ɂ�����i���̐����A�Z�L�����e�B���h�ЁE�ЊQ��̑��i�A��ƌo�c�ɂ�����IT���p�⍑�ۋ����͂̋����A���ۍv���Ȃǂł��B
���N��1���ɔ��\���ꂽ���{�́uIT�V���v�헪�v�ł́A�Љ�\�������v���Ă����|�e���V�������߂�IT�̓����𗘗p�҂̎��_�ɗ����ėL���Ɏg���A����������Y�Ƌ����͂̌����}��ƂƂ��ɁA���{�Љ�̕�����ۑ�̐��X�����v���Ă����ׂ��Ƃ��Ă��܂��B���̂��߂̖ڕW�Ƃ��āA�u���ł��A�ǂ��ł��A���ł��A�N�ł��v�g���郆�r�L�^�X�ȃl�b�g���[�N�Љ���������邱�Ƃ��f���Ă��܂��B
�uIT�V���v�헪�v�Ɏ����ꂽ����̏d�_�{��̂����ɁA�u���E��֗��Ō����I�ȓd�q�s���v���������Ă��܂��B���łɓd�q�\����d�q�\���Ƃ��������x���݂����^�p���J�n����Ă��܂����A����炪���p�������Ɏ������ɂ́A�d�q�����@�ie�����@�j�̐��肪�傫���ւ���Ă��܂��B�d�q�����@�Ƃ́A2004�N11���ɐ��肳�ꂽ�A�ۑ����`���t����ꂽ�����̓d�q����F�߂�@���ł��B
���[�ނ�������\�A�������̋c���^�ȂǁA���@��Ŗ@�ȂǂŊ�Ƃɕۑ����`���t�����Ă��镶���ɂ��āA�d�q�����ꂽ�����t�@�C���ł̕ۑ���F�߂Ă��܂��B�܂��A���̕������X�L���i�œǂݎ�����摜�f�[�^�����̗v�������Ό��{�Ƃ��ĔF�߂��܂��B
����ɂ��A�r�W�l�X��i�߂��ŕK�v�Ƃ���镶���E���[�ނ̈E���ʁE�ۑ��ɂ�����R�X�g���啝�ɍ팸����A��Ɗԏ�����̓d�q���������������i�����Ɗ��҂���Ă��܂��B
NPO�@�l �n�����i�@�\�����̔ȏ㕶�����ɂ��ƁA�d�q�\���̃����b�g�͏]���̐ŗ��m�̋Ɩ����y�����邱�ƁA�d�q�\���̃����b�g�͎����̂ł̎d��������Ǝ҂ɂƂ��āA���D���̎�Ԃ��Ȃ��邱�Ƃ��ƌ����܂��B����܂ŋƎ҂́A�����̂��ƂɋƎғo�^������K�v������܂������A�����s�ł͈ꊇ�o�^���\�ɂȂ�܂����B����͂��̑��̎����̂ɂ������������������L�܂邱�Ƃ����҂���܂��B
�@�S���ɂ́A��������IT���A���Ȃ킿�d�q�����̂̍\�z�A�n���ɐ�i�I�Ɏ��g�ޒn�悪�����������܂��B���̂����������Љ�܂��傤�B
�_�ސ쌧���{��s�́A�d�q���D�V�X�e�����������������������ƂŒm���Ă��܂��BIT�����p����BPR�i�Ɩ��v���Z�X���P�j�����H���钆�ŁA�Ɩ��̌������ƍs���葱���̌���A���D�ɎQ������Ǝ҂̗��������߂�d�q���D�̕K�v���������F�����A���{����悤�ɂȂ����ƌ����܂��B���݂́A����17�N����3�J�N�v��Ŏ��g��ł���u�ׂ��s�������i�v��v���g�s�b�N�ł��B����́AIT�����ʓI�Ɋ��p���Ȃ���A�L��E�����A�g�Ȃǂ̂悤�ɁA�s���T�[�r�X�����g�g�݂�ς��邱�ƂŁA�Z���ɂƂ��ĕ֗��ȃT�[�r�X�������𐮂��邱�Ƃ��ړI�ł��B��̓I�ɂ́A�R�[���Z���^�[�̐ݒu�A�����������A�C���^�[�l�b�g�ɂ��s�����T�[�r�X�̏[���Ȃǂ��d�_�{��Ƃ���Ă��܂��B
�����s�O��s�́A�s�̃z�[���y�[�W���Z�������Ǝ��ƎҌ����ɃJ�e�S���C�Y���邱�ƂŁA���p���������߂Ă��܂��B���ƎҌ����̃y�[�W�ł́A���D�E�_������܂Ƃ߂Čf�ڂ��A�N�ԍH�������\���H�����D�\��y�ь��ʁA�_��Ɋւ���e���Ɋւ�����Ȃǂ����J����Ă��܂��B���̑��A�������D�Q�����i�Ǝғo�^����A�������D�Q�����i�R���\���Ɋւ�����A���D�E�_��Ɋւ��鏑���ꗗ�ȂǁA���ɗL�����̍����d�g�݂��\�z����Ă��܂��B
���̑��A�_�ސ쌧����s�́u�s���d�q��c���v�i����s�̃z�[���y�[�W��ŁA�s���Ɋւ��邱�Ƃ���g�߂Ȑ����̘b��A�n�����Ɋւ�邱�Ƃ܂ł��܂��܂Ȉӌ�����̌������s���l�b�g���[�N��̃R�~���j�e�B�j��A�F�{������s�̒n��SNS�i��ɍЊQ���̂��Ƃ�j�Ȃǂ����ڂ��W�߂Ă��܂��B
����炪�B�����ꂽ�w�i�ɂ́A�e�����̂ɂ�鎎�s�������v�̂��߂̎u�����邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��A�n��̏Z���ɂ��ϋɓI�ȎQ���ӎ����傫���e�����Ă���ƌ����܂��B���������Ď��g�ނ��炱���A��i�I�ȓd�q�����́A�n�����B������Ă���̂ł��B
�Ăєȏ㎁�ɂ��ƁAIT���̃����b�g�͂܂��A���ԃ}�[�W���������Ȃ����ƂŃR�X�g�ጸ���ł��邱�Ƃ��ƌ����܂��B�����ɁA�������v����菜����A�Љ�̂��̂̕ϊv�𑣂��_�C�i�~�Y���Ɍq���邱�ƂŁA�]���̏��i�����P�p�ł��A����ɁA�n���I�E��ԓI���Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA�n��i�����������A�r�W�l�X�`�����X���S���ɕ����ɍL���邾�낤�Ƃ������Ă��܂��B
���Ȃ��̏Z��ł���n��ł͓d�q�����̂̎��g�݁A�n���̐i�W�͂������ł����B���͔M�S�Ɏ��g��ł���̂ɂ��܂�m���Ă��Ȃ��Ƃ����������钆�A��ƂɂƂ��Ă��A�l�ɂƂ��Ă��A�L�v�ȏ�������I�ȃV�X�e���������Ƃ��Ă��邩������܂���B�܂��́A�����̂̃z�[���y�[�W�����Ă݂邱�Ƃ���n�߂Ă݂Ă͂������ł��傤���B